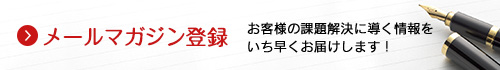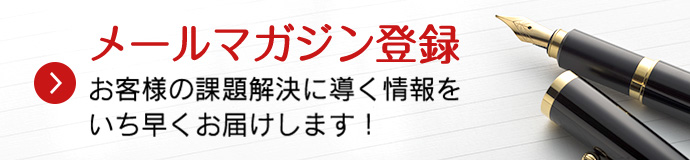薬剤師によるポリファーマシーの取組とは
高齢化が進む中で、ポリファーマシーの問題が浮上してきています。ポリファーマシーには明確な定義はありませんが、一般的には「必要以上に薬を飲んでいる状態で、患者の体に有害事象が起こっていること」を言います。多剤併用と不適切処方の認識が急速に高まる中、ポリファーマシー防止のために薬剤師がどう貢献できるか、効果的な方法を考えてみましょう。
ポリファーマシーは、多剤併用すれば必ず起こるというものではありません。10種類以上服用していても、問題がない場合もありますし、たった3種類でも類似薬の重複や薬物間相互作用、飲み間違いなどの問題が起こる可能性もあります。
高齢化が進む中で多剤併用療法も増えてきています。ポリファーマシーを防ぐために処方の適正化を行う必要性が求められています。
ポリファーマシーを防ぐために薬剤師ができる取組とは
薬剤のスペシャリストとして、薬剤師は処方や薬に関する情報を医師と患者さんの双方に提供し、情報の橋渡しができるようになることが必要です。
そのために
(1)薬剤、処方に対する良質の情報を入手しておく
(2)患者との良好なコミュニケーションをとれるようにする
(3)処方に疑問があった場合、医師に問い合わせる「疑義照会」を行う
という三つのポイントを心がけることが重要です。
疑義照会は薬剤師法で決められている薬剤師の務めですが、ポリファーマシーを防ぐために非常に大切なことです。
お薬手帳を活用して、ポリファーマシーを防ぐ
ポリファーマシーを防ぐには、患者さんも薬の正確な情報を知る必要があります。
高齢者を中心に、複数の病院にかかっている患者さんは重複投薬などポリファーマシーの問題に直面しています。薬の重複は健康被害を引き起こす可能性があり、不必要な薬を飲まないためには、「現在、どんな薬を飲んでいるのか」を知っていることが大切です。そのためには、お薬手帳を活用することがポイントとなります。
お薬手帳は「今まで飲んだ薬の履歴書」です。どんな薬が処方され、処方された薬をまだ飲んでいるのか、お薬手帳があれば把握できます。これによって薬の重複処方を防ぐことができるだけでなく、患者さんにも処方されている薬について、正確な情報を伝えることができます。
ポリファーマシーを防ぐためにも、お薬手帳は患者さんを知る重要なツールであると捉え、能動的な投薬指導を心がけましょう。
まとめ
高齢者を中心として、複数の病院にかかる人は今後も増えていくでしょう。複数の医療機関から処方された薬に重複はないか、飲み合せても問題がないかを判断できるのは薬剤師です。
薬剤師は豊富な薬の知識をもとに「不必要な薬を減らすこと」ができます。複数の医療機関から出された処方内容について、薬学的見地から「なぜこの薬が処方されたのか」を判断し、出された薬をしっかりと飲むことを指導できるのも薬剤師です。多剤併用する患者さんが増えている中、適切な薬の服用のために、薬剤師はとても重要な役割を担っていると言えます。
このように患者さんの動向を一元的に管理し、場合によっては医師に対して処方提案を行うなど、かかりつけ薬局・薬剤師の存在はますます大きくなってきています。弊社が提供するモバイル電子薬歴「iMelhis」では、患者さんの体質・アレルギー歴・副作用歴・服用状況などをしっかりと「見える化」することができます。持ち運べるモバイル端末によって、薬局内だけでなく在宅医療の支援も可能にし、サービスレベルの向上と効率化を図れます。
詳しくは、弊社担当者もしくは、第三事業本部営業第一部第二課(03-5309-0626)までお問い合わせください。
おすすめ商品
24時間、いつでもどこでも必要な薬歴情報の参照と入力が可能なモバイル電子薬歴「iMelhis」で、サービスレベルが向上します。ぜひご検討ください。
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら