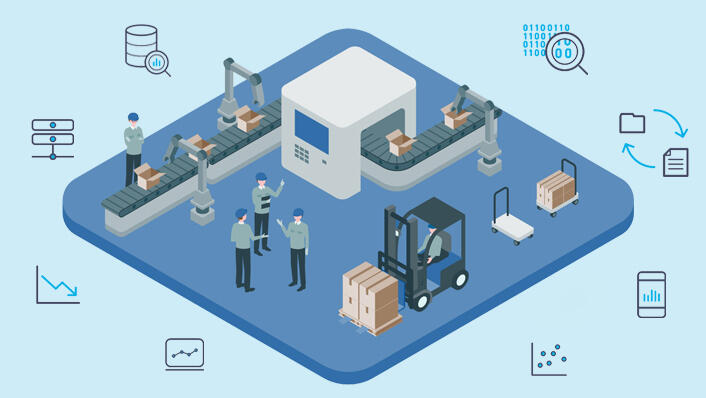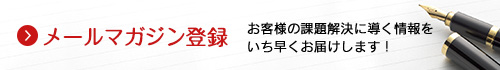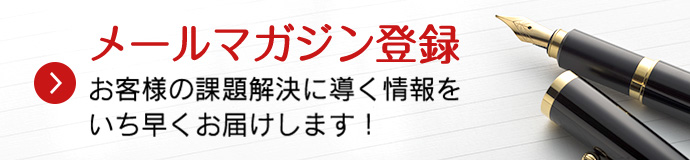生成AIで変わるモノづくりの現場力 - AI時代に求められる製造現場の人材育成
世界中で生成AIの活用が急速に進んでいます。ChatGPTに代表される生成AIは製造業でも活用され、図面の理解効率化や設備保全のナレッジ共有、品質管理の高度化など、製造現場に革新的な価値をもたらしています。
しかし、生成AIの活用には「AIによる判断は安全なのか」という慎重論から、「AIを使えなければ取り残される」という不安まで、様々な声が混在しています。一方で、経営層は「AI活用による生産性向上」への期待を高めていることでしょう。
本記事では、生成AIが製造現場で実際に活用されている事例やメリットをはじめ、現場のスタッフがAIを使いこなすための段階的アプローチ、人間とAIの協働の在り方まで、実践的な視点で詳しく解説します。
【目次】
- はじめに:AI時代の製造現場が直面する課題
- 生成AIが製造現場にもたらすメリット
- 現場のスタッフが生成AIを使えるようになるための実践的アプローチ
- AIの限界を理解し、適切に評価・活用するスキル
- 将来の製造現場の進化とAI活用の展望
- AI時代に求められる人材育成戦略
- 明日から始める実践的な導入施策
- まとめ:持続可能なAI活用体制の構築に向けて
はじめに:AI時代の製造現場が直面する課題
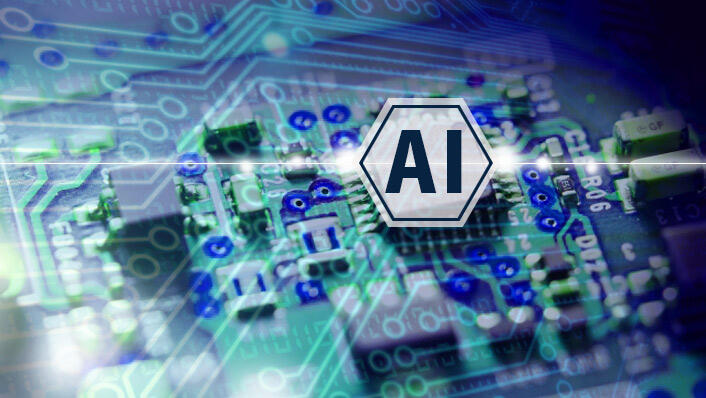
指示(プロンプト)に応じたAIが、学習したデータを使って文章や図表を自動で作成する技術を生成AIと言います。
製造業界は今、生成AIを含むAIと「どう向き合うか」という重要な局面を迎えています。ChatGPTをはじめとする数々の生成AIがリリースされて進化し、ルーティンワークに限らず、これまで人間が行なっていた創造的な作業の一部もAIがサポートできるようになりました。
しかし、多くの製造現場では、この先進的な技術をどのように活用すべきか模索していることでしょう。「AIの判断に任せても安全か」という慎重な意見や、「AIを使えなければ開発競争や市場で取り残される」といった心配な意見も出ています。一方で、経営層は「AI活用による生産性向上」への期待を寄せていることでしょう。
AI活用に課題を持つ現場が多い状況で、製造現場の人材育成を担う方々は、技能継承に加えて、“AI時代に適応した新しい人材育成の在り方”を検討されていると思います。
生成AIが製造現場にもたらすメリット
ここからは、生成AIが製造現場にもたらす具体的な効果や、生成AIの活用に必要なスキルを身につけるための人材育成について説明します。
生成AIは、製造現場に実用的な価値をもたらしています。まずは、5つの事例を見ていきましょう。
1. 図面の理解を促進
図面の理解は、経験の少ないスタッフにとって大きな壁の一つとなっていました。これまで図面の理解に数時間を要する場合もありましたが、生成AIが図面の内容を自然言語で解説することで、理解するまでの時間が大幅に短縮されます。
例えば、生成AIが「この部品は〇〇の機能を持ち、△△との関係で配置されています」といった具体的な説明を提供することにより、経験の少ないスタッフもスピーディに設計意図を把握できるようになりました。
また、パーツ同士の関連性などに疑問がある場合、生成AIに質問することで回答してくれます。図面の作成時に「何を追加で設計しないといけないのか」を生成AIに問うことで、新たな案を得ながら進めていくことも可能です。
2. 設備保全のナレッジを効率的に共有
設備保全の分野では、熟練技術者の知識を生成AIが学習し、故障の原因究明や修理手順を実用的なレベルで提案できるようになったと言われています。
これにより、地方拠点の工場も本社と同等の保守作業品質を実現することができます。例えば、地方拠点で設備の不具合が起きた際に、該当設備に詳しい熟練技術者の派遣を待つことなく、生成AIに修理方法や真因の特定手順を教えてもらうことができます。
膨大なマニュアルや設備設計ドキュメントを熟知した熟練技術者の経験に依存していた保全業務が標準化され、“知識の属人化”という課題が解決されつつあると言えるでしょう。
また、設備保全に関する定期点検の記録に対して、過去のトラブル事例を学習した生成AIに、交換が望ましい部品や追加点検すべき項目などの提案を依頼することも可能です。
3. 手順書の自動生成
製造品の試験・製造確認、在庫確認、検品、発注など、製造現場における各種作業手順書の作成は多くの時間を要する作業でした。生成AIは、手順書の作成に必要な情報を取り入れながら自動で生成することができます。
熟練技術者の暗黙知を生成AIが形式知化し、手順書に落とすことで技能継承のボトルネックが解消され、誰でもアクセスできる形で知識が蓄積されるようになった事例があります。
4. 品質管理の高度化
品質管理の領域では、生成AIによる画像解析技術の活用が進んでいます。ある工場では、検品時に不良品を識別する精度が従来の手法と比較して大幅に向上し、生成AIが品質安定性の確保に大きく貢献しています。
人間の目では見落としがちな不具合も、生成AIが継続的に検知することで、より安定した品質管理が可能になりました。検品スピードも人間より速く、品質管理に加えて検品チェックの効率化を実現できます。
5. 技能継承を効率的に実施
技能継承の場面でも、生成AIは大きな役割を果たしています。現場の知恵と生成AIの高度な処理能力を組み合わせることで、これまで熟練技術者の勘や経験に頼っていた作業を、経験の少ないスタッフも高いレベルで実行可能です。
具体的には、大量の音声データ、画像、ファイル、図面などに対して、生成AIによる質疑応答機能を活用することで瞬時にスタッフの疑問を解消することができ、技能継承のスピードが格段に向上しています。
現場のスタッフが生成AIを使えるようになるための実践的アプローチ
現場のスタッフには「生成AIは難しそう」という不安が少なからずあるかもしれません。こうした心理的なハードルを解消するために、段階的に生成AIを導入していきましょう。
初級段階
初級段階では、日常業務の一部を「生成AIに質問する」ことから始めましょう。例えば、「この工具の使い方は?」「類似トラブルの過去事例は?」といった、現場でよくある疑問を生成AIに質問し、その回答を得ることで生成AIの有用性を実感します。
次のステップとして、報告書や手順書の下書きを生成AIに作成させて、人間が修正を加える“協働”スタイルへの発展を目指しましょう。
ただし、どの生成AIツールを使えるかは会社や部門によりルールが設けられている場合があります。生成AIツールの活用を検討する際には、部門長や工場長など責任者に確認してから始めましょう。
中級段階
中級段階では、現場固有のデータ蓄積と同時に、蓄積したデータを学習した生成AIツールを活用しましょう。
例えば、自社で作成した図面や過去の不具合情報をクラウドストレージに蓄積し、蓄積したデータを生成AIツールに学習させて利用することで、より精度の高い回答を得られるようになります。生成AIの活用が進むことで、生成AIの出力レベルや利用方法を現場感覚で評価し、最適化する「AI教育」のスキルも身につけます。
この段階における“最適化”とは、生成AIに対する指示や質問の限界を理解することです。例えば、「これらのデータセットからカテゴリ別に点検結果を集計して」という指示を出した際に、ツールによってはExcelやCSVで処理できず、テキストファイルの送付が必要な場合があります。
また、「製造設備の活用事例を探して」という指示は、Webブラウザを検索できる能力を持たない生成AIツールの場合は利用できません。こうした場合は事例を探し、その事例の画像やテキストを入力した上で「この設備の活用事例を100字でまとめて」のように、内容をおきかえて指示を出しましょう。
上級段階
上級段階では生成AIの精度を上げ、生成AIの利用を広めていくことに注力すると良いでしょう。
生成AIに指示を出す文章は「プロンプト」と呼ばれます。「どのようにプロンプトを作成すれば回答精度が上がるか」と試しながら、「成功したプロンプトをフォーマットとして、類似の質疑応答に再利用する」といった活用ノウハウを蓄積することで生成AIの利用が定型化し、組織内での利用促進が進みます。
例えば、生産計画の立案を進める際に、必要な部品の種類や数、注意点について、社内データを基に生成AIからの回答を求めるには、
「過去の類似の生産計画を3つサンプルとして与える」
「どのような回答をしてほしいか、回答例を与える」
「どのような観点をカバーし、このくらいの文字数でアウトプットするなど、回答の方向性を含めた質問にする」
と、具体性を高めて指示を出すことで、生成AIの回答精度が格段に上がり、何度も生成AIとのラリーを続ける必要がなくなるでしょう。
生成AIの活用時における大切なポイントは「完璧を求めず、小さく始めること」です。失敗を恐れずに試行錯誤を重ね、現場の実情に合わせて生成AIをカスタマイズする姿勢で取り組むことで、生成AIを効果的に活用できるようになります。
AIの限界を理解し、適切に評価・活用するスキル
AIには多くのメリットがありますが、全ての問題を解決できるわけではありません。製造現場でAIを有効活用するには、AIの限界を正しく理解し、出力結果を適切に評価する「現場感覚」が不可欠です。
AIの苦手分野を把握する
AIは「法則性のないイレギュラーな事象」や「文脈に依存する判断」を苦手とします。
例えば、「このねじが少し緩い」という微妙な判断や、過去の経験に基づく直感的な判断は、依然として人間が担う領域です。
ある自動車部品工場では、AIが提示した改善案を現場の熟練技術者が検証し、「理論上は正しいが、この環境では適用困難」と判断したケースがありました。
生成AIの出力に対する検証スキルを把握する
生成AIを活用する際には「生成AIが言ったから正しい」ではなく、現場の実情と照らし合わせて妥当性を判断する能力を養うことが必要です。具体的には、生成AIの提案内容の実現可能性、安全性、コスト効率を多角的に評価し、必要に応じて調整や改善を加える技術を身につけることが求められます。
特に、事例が少ない場合やWebブラウザに情報が出回っていない情報を扱う業務に生成AIを利用する際には注意が必要です。「生成AIに必要な情報を教えた上で、回答を求めているか」という視点を持つようにしましょう。生成AIを「協働パートナー」として捉える視点を持ち、生成AIの処理能力と人間の現場感覚を組み合わせることで、高度な課題解決が可能になります。
「現場の暗黙知を生成AIに学習させ、生成AIの分析結果を現場の知恵で検証する」といった、相互補完的な関係を構築することで、真の生成AI活用が実現できるでしょう。
将来の製造現場の進化とAI活用の展望
近い将来、製造現場ではAIが日常業務に統合され、人間とAIの協働が定着する可能性が高いと考えます。現在の「AIを使える人 / 使えない人」という区分けは消え、全てのスタッフがAIパートナーと共に働く時代へと変化するかもしれません。
例えば、
▼設計において、AIが過去の設計データから最適解を瞬時に提案し、人間がそれをクリエイティブに発展させるプロセスが定着
▼製造工程において、AIが個々の作業者のスキルレベルに合わせてリアルタイムで指示・配置を調整し、品質向上と技能習得を同時に支援
▼予防保全において、AIが機械の「体調」を常時モニタリングし、故障前にメンテナンス指示を出すだけでなく、最適な交換部品まで提案
と、いった活用可能性が考えられます。AIとの協働環境において、人間に求められるのは、
■AIを導入・活用する「プロセスの設計」
■AIが理解できない「価値判断」や「創造的な思考」
■現場の文脈に基づく「最終的な決定」
の3つとなるでしょう。
AI時代に求められる人材育成戦略
AI時代における製造現場の人材育成は、初級・中級・上級のスキルレベルで人材育成を体系化すると良いでしょう。例えば、
▼初級(利用開始1年以内)では、基本的なAIツールを触りながら操作方法を習得
▼中級(利用開始から2~4年)では、業務プロセスへの導入スキルを高めるとともに、AI利用のリスクや限界を理解
▼上級(利用開始から5年以上)では、AIと協働する仕組みを設計し、組織内で横展開するスキルを得る
といった、具体的な項目を設定して人材育成に取り組むことがポイントです。
熟練技術者の暗黙知をAIが理解できる形で蓄積しながら、経験の少ないスタッフに技術を学ばせる「デジタル技能継承」プログラムも重要です。例えば、VR / ARを活用するなど、失敗が許される安全な環境で体験型学習を進めると良いでしょう。
また、AIがスタッフの習熟度を分析し、パーソナライズされた学習プランを提案することも可能です。ある機械メーカーでは、VR環境で機械の組み立てを練習し、AIが作業効率と安全性を評価するシステムを導入し、スキル習得期間を短縮させました。
AI時代の育成として、最も重要なポイントは「AI使いこなし人材」から「AI協働人材」に育成方針を転換することです。
「AIに仕事を奪われる」と危惧するのではなく、「AIを活用することで、創造的な業務に取り組める人材を育てられる」と捉えることで、技術進歩に強い組織文化を構築できるでしょう。
そのためには、AIを身近に感じられる事例や成功事例の共有をはじめ、十分に時間を確保してハンズオンなどの研修を実施するなど、継続した取り組みが重要です。
明日から始める実践的な導入施策
AIの活用は「まずは小さく始めること」が成功の鍵であることをお伝えしました。大規模なシステム導入を目指す前に、まずは現場ですぐに取り組めることから始めましょう。
最後に“小さく始める”ための実践的な2ステップを、ご紹介します。
第一段階
まずは、AIツールの試行を開始します。作業報告書の下書きをChatGPTで行なうなど、現場スタッフに実際に触れてもらいましょう。「AIってこんなに簡単なんだ」という体験を得て、AI活用への抵抗感を取り除くことが大切です。
ただし、機密情報を扱う場合や、技術漏洩を防ぐために社内でAIツールの利用が制限されている場合は、必ず上長に相談しましょう。
第二段階
次のステップは、特定業務におけるAIのテスト・導入です。
図面の解説の作成、トラブル対応マニュアルの更新、品質チェックリストの作成など、現場の困りごとを解決するために、ピンポイントでAIを活用し成功体験を積み重ねます。
なお、こうした場面ではChatGPTやCopilotなどのAIツールが利用可能です。Microsoft Copilotは、社内のドキュメントやデータをAIの利用データとして活用可能です。AIツールは数多くリリースされているので、調査してみましょう。
AIを活用したSaaSの場合、社内ナレッジベースの構築なども含め、導入には約3ヶ月以上かかることがあります。ナレッジベースの構築は熟練技術者の知識を整理し、AIが理解できる形でデータ化し、現場固有の専門用語や暗黙知を含む「自社専用AI」の基盤を作るプロセスが必要です。
AIの導入は、まず小さく始めつつ、ナレッジベースの構築が必要かどうかを見極めていきましょう。見極める際には「現場の課題を解決できるか」「費用対効果が合うか」がポイントになります。
まとめ:持続可能なAI活用体制の構築に向けて
AIは製造現場に革新的な変化をもたらします。そして、AIの真価を発揮させるのは技術そのものではなく、AIの特性を理解した人材です。
本記事で解説したように、図面の理解効率化、設備保全のナレッジ共有、品質管理の高度化など、AIは確実に現場力を向上させています。
AIの導入時に大切な視点は、AIと協働する仕組みや体制を意識し、まずは小さく始めることです。「AIは人間の能力を代替する存在ではなく、拡張する存在」として位置づけ、現場の暗黙知と組み合わせることで、新たな価値を創造できます。
変化を恐れるのではなく、変化を力に変える。それこそが、AI時代に求められる製造現場のマインドセットと言えるでしょう。小さな一歩が、将来の現場を大きく変えるきっかけになります。
AIネイティブを育てる人材育成は、日本の製造業が世界で勝ち続けるための戦略的投資とも言えます。技術革新と現場力の融合により、新たなモノづくりの時代を切り拓いていきましょう。
著者プロフィール

原田 正和
ITコンサルタント/エンジニア
東京大学卒業後、多彩なキャリアを通じてIT・DX分野の知見を蓄積。Big4コンサルティングファーム(監査法人)でのITコンサルタント、ITスタートアップでのエンジニア、エネルギーファンドでのシステム部長を歴任。SaaS導入支援やデータ基盤構築のコンサルティングを手がける。Microsoft365/Azure/Power Platformのエンジニアとしても活動中。マニュアル動画視聴システムの個人開発・販売実績を持ち、各種SaaS導入支援やDX伴走支援を通じて、企業のデジタル化を支援している。
「経営・マネジメント」の最新記事
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら