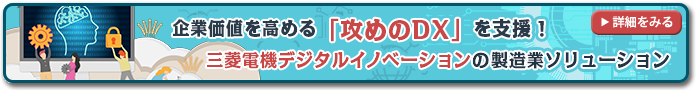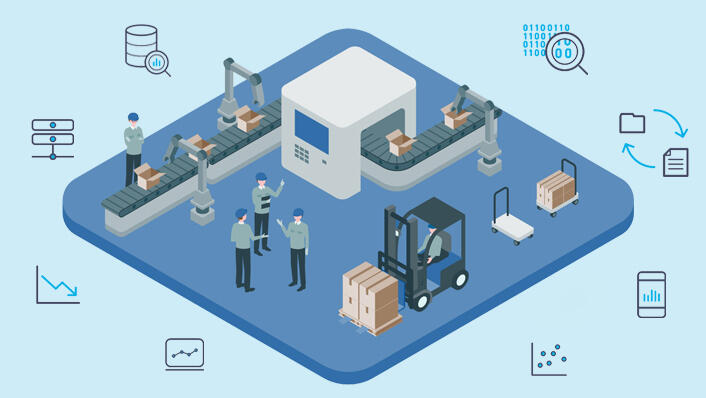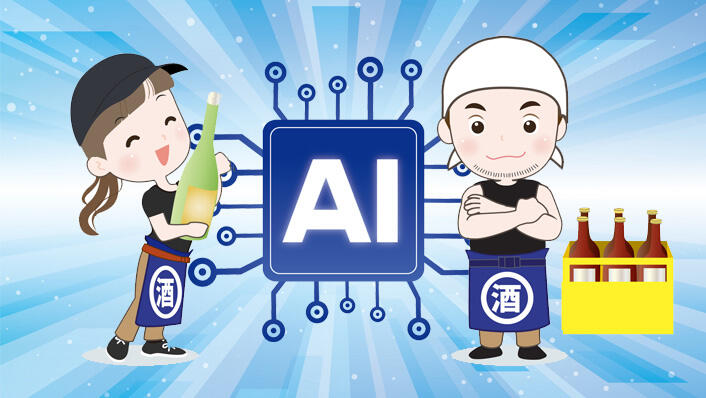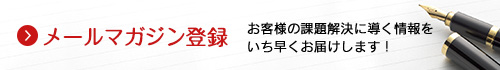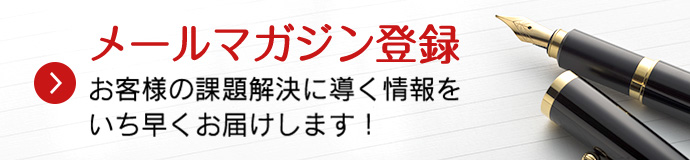"使わされる"から"使いたくなる"へ 現場浸透を実現する製造業向けシステム導入の新常識
製造業や倉庫業各社において、経営層主導でシステム導入を進めたものの、現場で思うように活用されていないという課題を耳にします。投資費用に見合う効果が得られず、従来の紙やホワイトボード、Excelによる業務が併存している状況は珍しくありません。
経営層が描く効率化のビジョンと、日々の業務に追われる現場担当者の実感との間には、大きな溝が存在する状況と言えるでしょう。
この記事では、「使わされるシステム」から「使いたくなるシステム」への転換方法について、技術導入における人間的・心理的側面にフォーカスしながら、システムの導入・浸透を成功するためのポイントを解説します。
【目次】
- システム導入が進まない理由
- なぜ現場はシステムを敬遠するのか?
- トップと現場をつなぐ「共感」の重要性
- 現場の“痛点”を起点としたシステム設計
- 成功体験の見える化でシステムの浸透を加速
- システム導入で実現する働き方改革
- まとめ:現場浸透を成功させるパートナー選び
システム導入が進まない理由

製造現場では、生産管理システムを導入したにも関わらず、作業指示書は相変わらず紙で配布され、進捗管理は手書きのボードで行われている場合があります。また、倉庫現場でも同様に、在庫管理システムがあるものの、実際の棚卸しや入出庫作業は紙ベースの台帳に頼っているケースが目立ちます。
このように、システム導入が進まない主な理由として、システムに不慣れな現場担当者の心理的な抵抗が挙げられます。
例えば、「長年培った業務手順の方が分かりやすい」「新しい操作が分かりにくく覚えられない」「なぜ今まで通りの方法を変える必要があるのか」といった声が、システム活用への大きな障壁となっています。
IT担当者は、システムの導入効果を数値や理論を通じて説明し、納得してもらおうとしますが、現場とのギャップは埋まらず、結果として現場担当者が「使わされている感」だけを感じる悪循環が生まれがちです。
こうした状況を打開するためには、従来の「トップダウン」による強制的なシステム導入から脱却し、「共感」を軸とした新たなアプローチが不可欠です。単なる技術導入ではなく、人間的・心理的側面に踏み込んだ、真に現場に寄り添うシステム導入戦略が求められています。
なぜ現場はシステムを敬遠するのか?
現場担当者がシステムを敬遠する理由は、単に「ITが苦手」という表面的な問題だけではありません。
心理的な抵抗感
最も大きな要因と考えられるのは、長年慣れ親しんだ業務フローや手順を変更することへの心理的な抵抗感です。
製造現場では、「紙の作業指示書なら一目で全体が把握できる」「手書きメモならすぐに追記できる」といった実用性への信頼があります。
また、倉庫現場でも「手書きの台帳なら電源も不要で確実」「慣れた手順なら間違いが少ない」という安心感が根強く残っています。
不信感の増大
さらに深刻な理由として考えられるのは、システム導入の目的や必要性が現場に十分に伝わっていないことです。
経営層は効率化やコスト削減を重視しますが、現場担当者は「今でも問題なく業務は回っている」「なぜ変える必要があるのか」という疑問が生まれがちです。
こうした認識のズレが、システムへの不信感を増大させる要因となります。
ミスへの恐怖心
操作方法の習得に対する不安やミスへの恐怖心も大きな障壁となります。
特に、システムに不慣れな担当者にとって、新しい操作を覚えることは大きなストレスであり、「使いこなせなかったらどうしよう」という心配が先行してしまうのが実情です。
トップと現場をつなぐ「共感」の重要性
システム導入を成功させる最大の鍵は、経営層と現場担当者が相互に理解し合い、「なぜ変革が必要なのか」「変革をするには何がネックになりうるか」について思いを双方で共有することです。
双方の立場や課題を深く理解し合う、「共感」が生まれる関係性が欠かせません。
現場担当者主導の仕組みづくり
効果的なアプローチは、経営層からの呼びかけにより、現場担当者自身がシステム化の検討を主導する仕組みづくりです。
「会社の競争力向上のために、皆さんの知恵を貸してほしい」という経営層のメッセージが現場の当事者意識を喚起する一方で、現場からは日々の業務で感じている具体的な課題や改善点を率直に伝えてもらいましょう。
この議論の中で、経営層は現場の実情を深く理解し、現場担当者は会社全体の方向性や競争環境を知ることができます。
例えば、製造現場の「品質向上と作業効率化を両立したい」という願いと、経営層の「市場競争力強化」という目標が、実は同じ方向を向いていることに気づけるかもしれません。
また、倉庫現場の「ミスを減らしながら作業負荷を軽減したい」という思いも、経営層が目指す「顧客満足度向上とコスト最適化」と本質的に方向性が一致しています。
重要なポイントは、現場担当者が主体となってシステム化の必要性を検討し、「現場の課題を解決するために、このシステムが必要だ」という結論に自ら達することです。
経営層は現場の判断を支援し、「システム導入は現場の皆さんが提案してくれた解決策を実現する手段」として位置づけることで、協働関係が生まれます。
共感に基づく相互理解により、現場担当者は「押し付けられたシステム」ではなく「自分たちが選択したツール」としてシステムを受け入れ、積極的に学習し、導入するメリットを見出すことができます。
現場の“痛点”を起点としたシステム設計
現場に受け入れられるシステムの構築には、目の前の課題解決だけでなく、組織全体の戦略的な目標を見据えたアプローチも求められます。
現場の具体的な“課題=痛点”を起点としながら、全社的な生産性向上と将来的な成長を見据えたシステムの設計が重要です。
こうした、“痛点”ベースのアプローチこそが、使いたくなるシステムを生み出す鍵となります。
現場の現実的な課題と全体最適の両立
システム設計において重要なポイントは、個別の課題解決と全体最適のバランスを取ることです。
単に目の前の困りごとを解決するだけでなく、他部門との連携の有無や関連業務への影響も同時に考慮するとよいでしょう。
例えば、以下のような課題が製造現場と倉庫現場であるとします。
1.製造現場の具体的な課題例:
- 1-1「検品指示書の更新が間に合わず、古い情報で作業してしまう」
- 1-2「設備の稼働状況が分からず、段取り替えのタイミングを逃す」
2.倉庫現場の日常的な問題:
- 2-1「在庫数の不一致で出荷が止まる」
- 2-2「倉庫の検品指示書や手書き伝票の文字が読めず確認に時間がかかる」
この場合、検品指示書を最新情報で出力する機能をシステムに実装することで、上記1-1の課題が解決できます。
さらに、倉庫現場でも同じ機能で伝票出力を行えるようにすることで、2-2の課題も同時に解決され、全体最適化が進みます。
1-2や2-1などの他部門が関係しないものや、関連業務がないものについては個別に対応を考えてよいでしょう。
分かりやすく導入しやすい設計を
現場に受け入れられるシステムを構築するためには、機能の充実度だけでなく、使いやすさも重要な要素となります。
直感的な操作で確認できるダッシュボード機能などを実装する際も、システムに不慣れな担当者でも迷わず操作できるように、シンプルで分かりやすい画面設計が不可欠です。さらに、現場の業務フローを大幅に変更するのではなく、既存の作業手順に自然に組み込める形でシステムを設計することで、導入時の抵抗感を最小限に抑えることができます。
ただし、個別の現場での使いやすさを追求するあまり、部門間の連携や情報の一貫性が損なわれては本末転倒です。例えば、製造現場で使いやすい検品指示書の出力機能を設計する際には、倉庫現場でも同じ情報を活用できるよう、共通のデータ形式やアクセス権限を設定することが重要です。
全体最適を意識した設計により、一つの改善が複数の部門に波及効果をもたらし、結果として組織全体の生産性向上につながります。また、将来的な事業拡大や新たな部門の追加にも対応できる拡張性を持たせることで、システムの長期的な価値を最大化することが可能です。
分かりやすさと全体最適のバランスを取るためには、現場の担当者だけでなく、関連部門の責任者も含めた設計レビューを定期的に実施し、局所的な改善が全体に与える影響を継続的に評価し、改善することが効果的です。
成功体験の見える化でシステムの浸透を加速
現場でシステムの浸透を確実にするためには、導入効果を数値やグラフで示すだけでなく、現場担当者が実感できる「小さな成功体験」を積み重ねることが重要です。
現場に合った共有方法の実践
成功体験を組織全体で共有する仕組みこそが、システム活用の好循環を生み出します。
製造現場では「作業指示の確認時間が半分になった」「設備トラブルの早期発見で残業が減った」といった身近な改善効果を、担当者自身の言葉で表現してもらうことが効果的です。
倉庫現場でも「在庫確認のための歩き回りが不要になった」「入力ミスによる手戻り作業がなくなった」など、日常業務の負担軽減を具体的に実感できる場面を記録し、共有します。
導入後の変化のプロセスを追跡
成功体験の見える化に必要なことは、システムに不慣れだった担当者が徐々に操作に慣れ、最終的には「このシステムがないと困る」と感じるまで、変化のプロセスを追跡することです。
例えば、プロセスを写真や動画、担当者インタビューなどで記録し、社内報や朝礼で共有することで、まだシステムを使いこなせていない他の担当者にも安心感と意欲を与えられます。
なお、成功事例の共有は現場発信で行うことが重要です。管理者からの一方的な報告ではなく、実際にシステムを使用している担当者が自らの体験を語ることで、説得力のあるストーリーで訴求でき、組織全体の意識変化を促します。
システム導入で実現する働き方改革
適切な方法でシステムを導入した現場では、業務効率化にとどまらず、働き方改革も進みます。つまり、システムによる業務負荷軽減に加え、現場担当者にとって働きがいの向上をもたらし、新たな価値の創造も期待できます。
製造現場で期待できる効果
製造現場では、リアルタイムで生産状況を把握することにより、急な生産変更への対応がスムーズになり、残業時間の削減が可能です。
また、データ入力の自動化により、現場担当者は手作業による転記作業から解放され、品質向上や改善提案といった付加価値の高い業務に集中できるようになります。
倉庫現場で期待できる効果
倉庫現場でも同様に、在庫管理の精度向上により棚卸し作業の負担が大幅に軽減され、出荷ミスによる緊急対応やクレーム処理の頻度が減少します。
システムに不慣れだった担当者も、操作に慣れることで「自分もデジタル化に貢献できている」という達成感を得られ、仕事へのモチベーション向上につながります。
データ活用により根拠のある提案が可能に
さらに重要なのは、システム化により蓄積されたデータを活用して、現場担当者自身が業務改善のアイデアを提案できるようになることです。
これまで経験と勘に頼っていた判断が、データに基づいた根拠のある提案に変わり、現場の声がより経営層に届きやすくなります。
この変化こそが、現場主導での働き方改革を実現するのです。
まとめ:現場浸透を成功させるパートナー選び
過去にシステム導入を経験したことがない組織や、不安を抱える組織において、現場に浸透するシステムの導入を実現するには、技術的な機能だけでなく現場の心理的な変化を理解できるパートナーを活用することで、より安心して効果的にシステム導入を進めることができます。
優れたパートナーは、製造業や倉庫業の現場事情を深く理解し、システムに不慣れな担当者の不安や抵抗感に共感できる専門性とノウハウを持っています。
現場のヒアリングから始まり、“痛点”の発見、システム設計、操作などの教育、システム浸透の支援まで、一貫したサポート体制を提供することで、「使わされるシステム」ではなく「使いたくなるシステム」への変革を支援します。
システムの現場浸透に欠かせないポイントは、導入後のフォローアップ体制です。システムの運用開始後も定期的に現場を訪問し、担当者の声に耳を傾け、必要に応じてシステムの調整や追加教育を実施する姿勢が求められます。
また、成功事例の収集と共有について積極的にサポートし、組織全体での変革を促進することが重要です。
製造現場や倉庫現場でのシステム導入にお悩みの方には、現場の実情を理解し、経営層と現場の橋渡し役となれるパートナーとの連携をおすすめします。技術と人の心をつなぐパートナーシップを起点に、業務改革に着手しましょう。
三菱電機デジタルイノベーションは、製造現場向けの生産管理システムや、倉庫・物流領域でのサプライチェーンソリューションにおいて、長年にわたる製造業との向き合いで培った現場目線のアプローチを提供しています。
また、システムに不慣れな担当者でも直感的に操作できるシステム設計と、導入から定着までの現場密着型サポートにより、多くの導入実績を重ねています。
著者プロフィール

原田 正和
ITコンサルタント/エンジニア
東京大学卒業後、多彩なキャリアを通じてIT・DX分野の知見を蓄積。Big4コンサルティングファーム(監査法人)でのITコンサルタント、ITスタートアップでのエンジニア、エネルギーファンドでのシステム部長を歴任。SaaS導入支援やデータ基盤構築のコンサルティングを手がける。Microsoft365/Azure/Power Platformのエンジニアとしても活動中。マニュアル動画視聴システムの個人開発・販売実績を持ち、各種SaaS導入支援やDX伴走支援を通じて、企業のデジタル化を支援している。
「経営・マネジメント」の最新記事
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら