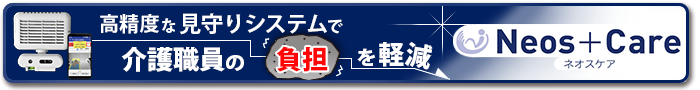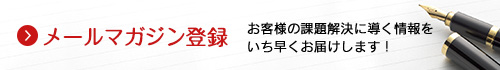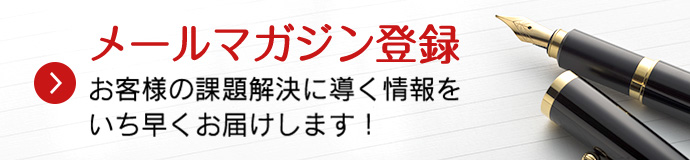介護施設における転倒事故の現状とは? 原因別に効果的な防止対策を徹底解説
介護施設での転倒事故の予防には、原因の洗い出しと効果的な対策の実施が必要不可欠です。そこで、本コラムでは、次の内容を現役の介護職員が現場の経験を活かし、分かりやすく解説します。
- 介護施設の転倒事故の現状
- 転倒事故の主な原因
- 原因別の効果的な対策
また、実際にあったさまざまな転倒事故の事例をもとに、事故の原因や対策を考える際のポイントもお伝えします。介護施設の転倒事故でお悩みの方は、ぜひ本コラムを参考に効果的な転倒事故対策をご活用ください。
介護施設における転倒事故の現状

まずは、介護施設における転倒事故の現状について見ていきましょう。
消費者庁新未来創造戦略本部の「高齢者の事故防止等に関するアンケート調査」によると、デイサービスでは、ご利用者が怪我をした、またはしそうになった原因は「つまずく、転ぶ、よろめく」といった転倒に関することが最も多いとされています。
また、一般社団法人日本転倒予防学会の「介護老人保健施設入所者の転倒発生状況」によると、介護老人保健施設利用者の事故459件のうち、およそ7割の304件が転倒事故であるということが分かりました。
高齢者は骨や皮膚が弱く、転倒事故による出血や骨折などの重大な怪我につながるおそれもあるため、効果的な対策が必要不可欠です。
転倒場所は居室が多く、転倒が発生する時間帯は午前2時〜午前4時と、夜中から早朝にかけて多く発生するデータも出ています。
参照:
消費者庁新未来創造戦略本部「高齢者の事故防止等に関するアンケート調査」
日本転倒予防学会誌 第2巻 第3号「介護老人保健施設入所者の転倒発生状況 ― 移動手段に着目して ―(P23)」
介護施設で転倒事故が発生する主な3つの要因
介護施設で発生する転倒事故は、主に3つの要因が考えられます。
- 利用者要因
- 介護者要因
- 環境的要因
これらの要因を多角的に捉えることが、転倒を防止するために重要なポイントです。ぜひ、この機会に理解していただき、転倒の予防を考える際に活かしてください。
では、それぞれ具体的な内容を確認しましょう。
利用者要因
利用者要因とは、主にご利用者の身体状況や精神的状態など、ご利用者自身が転倒リスクを高めているものです。
(例)
- 歩行能力の低下
- 認知症による判断能力の低下
- 薬の副作用による眩暈やふらつき
具体的には、認知症の影響でトイレの場所が分からない状態でご利用者が施設内を歩き回り、段差に気づかず転倒するケースです。
単純に歩行能力や判断力の低下だけでなく、薬の副作用や寝不足などの要因も重複することで転倒リスクが高まります。
介護者要因
介護者要因は、人員配置や人員不足など、施設で介護サービスを提供する介護職員に起因し、転倒事故のリスクを高めているものです。
(例)
- 人員不足による見守り不足
- 不適切な介護によるリスクの増大
- 疲労やストレスによる判断力の低下
介護業界では介護職員の不足をはじめ、残業や夜勤による長時間労働が問題になっています。
従事者の疲労やストレスが溜まることで、仕事中の判断力が低下するおそれがあります。判断力が低下することで介護サービスの質が下がり、適切な介助が行えずに転倒事故が発生するケースも考えられるでしょう。
環境的要因
環境的要因とは、介護施設内の設備や状況など、環境面が原因で転倒につながるものを指します。
(例)
- 滑りやすい床(特に浴室は要注意)
- 夜間の不適切な照明管理
- 不適切な履物や杖の使用
具体的には、ご利用者が水をこぼしてしまい、床が滑りやすい状態になり転倒したという事例があります。
そのほか、適切な場所に手すりを設置していないことにより転倒した場合も、環境的要因による転倒事故と言えるでしょう。
【要因別】介護施設での転倒事故を防ぐ効果的な対策
介護施設での転倒事故を防ぐために効果的な対策を、以下3つの要因別に解説します。
- 利用者要因の場合
- 介護者要因の場合
- 環境的要因の場合
それぞれの要因に対する転倒事故の事例と対策を紹介するので、効果的な対策を知りたい方はぜひご覧ください。
利用者要因の場合
▼歩行状態の低下が見られるご利用者の転倒
|
Aさんは、普段から自力で歩かれており、自分から積極的に散歩をしていたが、体調不良をきっかけに歩く機会が減り、ベッドで過ごす時間が増えた。最近は歩行中にふらつくことが多くなり、その結果、トイレに行く途中に転倒してしまった。 |
上記の転倒事故に対しては、以下の対策が効果的です。
- リハビリテーションにより歩行状態の維持や改善を図る
- 日常生活の中で職員付き添いのもと歩く機会を設ける
- 座ったままでもできる転倒予防体操を行う
ご利用者が自力で歩ける状態ならば、積極的にリハビリを活用し、歩行能力の安定を図ることが大切です。
▼薬の副作用によるふらつきが原因の転倒
|
Bさんは毎晩就寝前に、眠剤を内服している。最近は薬の副作用からか、朝方のふらつきが多く見られ、ある朝、職員がお部屋に伺うと、ベッド横の床に尻もちをついているところを確認した。 |
薬の副作用が原因で転倒事故につながっているケースは、以下の対策がおすすめです。
- 薬の内容や内服時間について医療職に相談する
- 医療職と相談後に内服薬の内容や内服時間を再検討する
- 睡眠状況を把握し不眠の場合は眠りやすい環境に配慮する
薬の副作用による転倒が疑われる場合は、必ず医療職と連携し、その後の対応を検討しましょう。
介護者要因の場合
▼人員不足による見守り不足が原因の転倒
|
Cさんは、自分から立ち上がり歩こうとされるが、自力歩行は難しく転倒のリスクが高い。本来は常時見守りが必要なご利用者だが、人員不足の影響もあり見守りができない時間があった。その結果、自分から立ち上がり、数歩歩いたところで転倒した。 |
人員不足が原因の転倒事故に対しては、以下の対策がいいでしょう。
- 勤務時間を臨機応変に変更し転倒事故が多い時間帯に人員を充足する
- 職員の動き方を変更し見守りが途切れないワークスケジュールにする
- 見守りが可能な転倒事故予防ができる見守りシステムを導入する
人員不足をすぐに解消することは難しいため、今いる人員で見守り不足のリスク軽減を行うことが大切です。
また「ネオスケア」のような、転倒事故の防止対策に効果的な見守りシステムを積極的に導入することで、見守り不足を解消する方法もあります。
▼不適切な介護が原因の転倒
|
Dさんは歩けるものの、目が見えないため付き添い歩行が必要。介助方法は職員が両手を持ち、ゆっくり声をかけながら行う必要がある。しかし、ある職員はDさんの隣で片手だけを持ち介助。その結果、Dさんは普段と違う介助方法に戸惑い、転倒した。 |
不適切な介護が原因による転倒事故は、以下の対策が効果的です。
- あらためて統一したケアについて職員間で話し合う
- 転倒事故を防ぐために必要な介護スキルの勉強会を行う
- 職員の心身の負担についてもヒアリングを行う
転倒事故が介護者要因の場合、単に介助方法が不適切なだけでなく、介護者自身の精神状態が影響しているケースもあるため、職員の悩みや疑問などをあらためて聞くのもいいでしょう。
環境的要因の場合
▼浴室での滑りやすい床が原因の転倒
|
Eさんは自力で安定した歩行が可能な方である。そのため、職員は入浴時も大丈夫だろうと思っていたが、浴室の床が滑りやすく、足を滑らせて転倒した。 |
浴室の床が滑りやすい場合は、以下の転倒予防対策がいいでしょう。
- 浴室内では常に職員が付き添い歩いてもらう
- 浴室に滑り止めマットを敷く
- 浴室用の滑り止めスプレーを使用する
浴室は濡れているため滑りやすく、職員でさえも転倒しそうになります。そのため、入浴介助時は常にご利用者に付き添い、転倒しそうになっても支えられるようにしておきましょう。
浴室は転倒リスクが非常に高いことを、常に頭に入れて入浴介助を行うことが大切です。
▼常に見守りできない居室内での転倒
|
Fさんを起こすために、早朝の6時過ぎにお部屋に伺うと、洗面台前で転倒しているFさんを確認した。Fさんによると「トイレに行こうとして転んだ」と言われる。 |
常に見守りできない居室での転倒には、以下の対策がおすすめです。
- こまめに訪室する
- センサーマットを利用する
- 転倒事故予防ができる見守りシステムを導入する
今回のFさんのケースは、トイレに行こうとして転倒しているため、排泄介助のタイミングを見直すのも効果的です。
転倒事故の原因や対策を考える際に大切なこと
転倒事故の原因や対策を考える際に大切なポイントは、以下の3点です。
- 原因を多角的に捉える
- 対策を実施した結果も分析する
- リスクをゼロにするのは難しいことを理解する対策を実施した結果も分析する
事故原因を徹底的に把握することで、より効果的な対策を立てられます。それぞれの具体的な内容を確認し、実際に事故対策を考える際に活かしてください。
原因を多角的に捉える
転倒事故の原因は一つではなく、事故の原因を多角的な視点で捉えることが必要です。たとえば、ふらつきのあるご利用者の場合、次のようなさまざまな原因が考えられます。
- 運動不足による歩行能力の低下
- 薬の副作用によるふらつき
- 昼夜逆転による寝不足
- 介護者の不適切な介護によるストレス
- 認知症症状の進行による判断力の著しい低下
ふらつきの原因自体は歩行能力の低下ですが、「なぜ歩行能力が低下しているのか」という考えに至ることが大切です。
職員の不適切な介護が、ご利用者のストレスにつながり、歩行状態の悪化をもたらしている可能性も考えられます。
また、「薬が合っていないのではないか」「寝不足でふらついているのではないか」など、さまざまな疑問を持つことで、詳しい原因が明確になり、効果的な対策が見えてきます。
転倒事故の原因は一つだけではないことを、職員間の共通認識として持っておきましょう。
対策を実施した結果を分析する
転倒事故が発生後、原因を導き出して対策を講じるだけでなく、対策を実施してどのような結果であったかを分析しましょう。
今後の支援方針を決める上でも、対策によってご利用者にどのような影響が起きたか確認することも重要です。対策を実施する中であまり効果的でないと気づく可能性もあるため、こまめに経過観察を行いながら、最も適した介助方法を検討する必要があります。
また、分析結果は必ず職員間で情報共有し、チーム全体で転倒防止に取り組むことが非常に重要と言えるでしょう。
リスクをゼロにするのは難しいことを理解する
転倒事故は骨折や出血外傷など、大きな怪我につながるリスクを伴います。また、転倒が原因で寝たきりになるおそれもあるでしょう。
しかし、転倒事故をゼロにすることは難しく、介護職員はそのことを理解した上で日々介護サービスを提供しなければいけません。
ご利用者のご家族に対しては「絶対に転倒させません」と言うのではなく、「常に転倒防止に配慮しても転倒のリスクがある」ことを事前に説明しておきましょう。
ただし、リスクをゼロにすることは不可能でも、限りなくゼロに近づけることは可能です。今できる対策を確実に行うことが大切になってきます。
まとめ
介護施設における転倒事故を効果的に防ぐためには、まず原因を多角的に考えることが重要です。なぜなら、さまざまな原因を洗い出すことで、効果的な対策が見えてくるからです。
効果的な対策は決して一つだけではなく、さまざまな角度からのアプローチが必要とされています。
本コラムで紹介した、転倒事故の原因や対策を考える際に大切なことを参考にすれば、介護施設における転倒事故のリスクを減らせる可能性があります。
リスクをゼロにすることは難しいですが、リスクを最小限に留めるためにも、職員全体で協力し継続的な支援を実施しましょう。その上で、効果的なシステムの導入も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
著者プロフィール

津島 武志
介護系WEBライター
介護業界16年目の現役介護職。介護リーダーや管理職の経験もあり、現在は地方法人のグループホームに勤務。現役の介護職以外に、介護系のWebメディアにおいてのライター活動をはじめ、介護士さんを応援するメディア「介護士の転職コンパス」や「介護士の副業アンテナ」などの運営にも取り組んでいます。主な保有資格は、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士。
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら