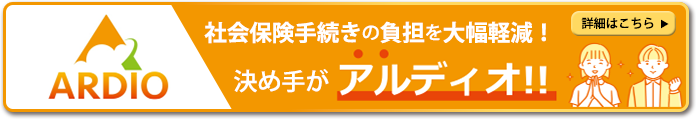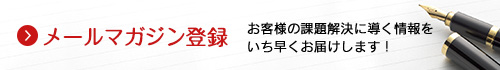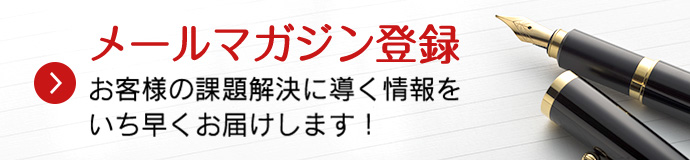雇用保険法改正のポイントは?適用範囲の拡大や給付金の創設などを解説
近年、非正規雇用の増加や少子化対策の必要性などを背景に、雇用保険制度の見直しが進んでいます。2025年には新たな給付制度が始まり、2028年には雇用保険の適用範囲が拡大される予定です。企業はこうした変化に対応するため、制度の理解と準備が求められます。
本記事では、今後の雇用保険法改正の全体像と具体的な内容を解説するとともに、企業が押さえておくべきポイントを解説します。
【目次】
- 雇用保険法改正の全体像
- 【2025年4月施行】出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設
- 【2025年10月施行】教育訓練休暇給付金の創設
- 【2028年10月施行】雇用保険適用拡大
- 今後の雇用保険法改正に伴う企業の対応
- まとめ:今後の雇用保険法改正に備えて早めの準備を
雇用保険法改正の全体像

今回の法改正は、企業が雇用保険の適用対象となる労働者の拡大や給付金制度の創設を通じて、働く人への支援を強化することを目的としています。
企業に影響がある主な改正点と施行時期は、以下のとおりです。
2025年(令和7年)4月1日:「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の創設
両親共に(配偶者が就労していない場合などは本人が)育児休業を取得した場合や育児のために時短勤務で就業する場合に支給される給付金が新たに創設され、育児と仕事の両立支援が拡大されます。
2025年(令和7年)10月1日:「教育訓練休暇給付金」の創設
教育訓練休暇を取得し、一定条件を満たした場合に支給される「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
2028年(令和10年)10月1日:雇用保険の適用条件が「週10時間以上」へ拡大
雇用保険の適用条件が従来の「週20時間以上」から「週10時間以上」へと拡大されます。
このように、雇用保険制度は段階的に見直しが行われる予定です。企業は制度の概要を理解し、計画的な社内体制の整備を進めていく必要があります。
【2025年4月施行】出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設
日本では、男性の育児休業取得割合の少なさが課題となっています。政府は、少子化対策や働き方改革の一環として「男性の育休取得率向上」を重要指標に掲げ、法改正や支援策を講じてきました。
その支援策の一つとして、2025年4月より「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました。
出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、育児休業を取得する従業員に対し、育児休業給付金に上乗せして支給される新たな給付金です。
共働き夫婦が子の出生直後に共に、育児休業を取ることを促進するため、一定の条件を満たした場合に育児休業給付金(出生育児休業給付金)とあわせて追加支給されます。
育児休業給付金は、育休開始から「180日までは賃金の67%」「181日目以降は賃金の50%」が支給されます。出生後休業支援給付金は、育児休業給付金に「最大で28日間、賃金の20%を上乗せし、育児休業給付金とあわせて80%の給付金」を支給します。
賃金の80%とは「給与の額面から、社会保険料や所得税等を差し引いた手取り額に相当する額」です。つまり、育児休業中最大28日間は、手取り相当額が支給されるということになります。
出生後休業支援給付金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①本人(被保険者)が14日以上の育児休業を取得したこと
②配偶者が14日以上の育児休業を取得したこと
ひとり親や専業主婦(夫)など、育児休業を取得する就労先がない場合は②の要件は必要ありません。
また、出生後休業支援給付金の申請時には、以下のいずれか一つを支給申請書に記入する必要があります。
- 配偶者の被保険者番号
- 配偶者の育児休業開始年月日
- 配偶者の状態(ひとり親や専業主婦(夫)などの場合)
詳しい内容や必要書類については、以下の「育児休業等給付の内容と支給申請手続」をご確認ください。
出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続 」
育児時短就業給付金
育児時短就業給付金は「2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して働く従業員に対して支給される」雇用保険の新たな給付金です。
従来、育児関連の給付金は主に育児休業が対象でした。育児時短就業給付金は新たに「時短勤務で働き続ける場合」の収入減少を補助する制度として、2025年4月に創設されました。
育児時短就業給付金の対象は、「雇用保険の被保険者として働く従業員」かつ「2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている従業員」です。
支給要件は、以下①②の両方を満たす必要があります。
①2歳未満の子を養育し、1週間あたりの所定労働時間を短縮し就業している
②育児休業給付金の対象となる育児休業から復帰し、引き続き時短勤務での就業を開始している。または、時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある
支給額は、原則として「時短勤務中の各月に実際支払われた賃金額の10%相当額」です。ただし「賃金+給付金」の合計が元の100%を超えないように調整されます。
なお、子が2歳に達した翌月以降は「法律上の3歳未満(3歳になる誕生日前日)」まで時短勤務が適用されますが、給付金の支援対象は2歳で終了します。
また、時短勤務を終了した月(フルタイム勤務に復帰した月)も対象外となります。ただし、その後に時短勤務を再開し、支給要件を満たしていれば、育児時短就業給付金が支給されます。
詳しい内容や必要書類については、「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」をご確認ください。
出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続 」
【2025年10月施行】教育訓練休暇給付金の創設
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の被保険者が職業に関する教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した際、その休暇期間中の生活費を支援する新たな給付金です。
働きながら自己啓発やリスキリングを行う場合、時間的・経済的な負担が課題となります。その負担を軽減する目的で、2025年10月に創設されます。
支給条件
教育訓練休暇給付金の対象は、雇用保険の被保険者です。また、給付を受けるには以下の要件を全て満たす必要があります。
- 被保険者期間が5年以上あること
- 休暇開始前の2年間に被保険者期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あること
- 就業規則や労働協約等に基づいて教育訓練休暇を取得していること
- 取得する教育訓練休暇の期間が30日以上であること
- 休暇中に給与が支払われていないこと
- 休暇終了後に解雇予定がないこと
また、原則として厚生労働大臣が指定する教育訓練給付金の対象講座を受講する必要があります。
給付内容
教育訓練休暇給付金の給付額は「失業給付の基本手当に相当する額」です。給付日数は以下のように被保険者期間に応じて「90日」「120日」「150日」のいずれかとなります。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
なお、教育訓練休暇が終了すれば給付金の支給も終了します。また、原則として教育訓練休暇の開始日から1年以内の期間に取得した休暇が対象となります。
申請手続きと事業主の対応
企業側の対応事項としてまず重要なのは、自社の就業規則に教育訓練休暇制度を整備することです。
厚生労働省の調査によれば、現状で教育訓練休暇制度を導入している企業は全体のわずか7.4%に過ぎません。従業員が教育訓練休暇給付金を受給するには、企業として制度を設けておく必要があります。
参考:厚生労働省「訓練期間中の生活を支えるための新たな給付や融資制度の創設について」
【2028年10月施行】雇用保険適用拡大
現行では「週20時間以上」の労働を条件としていた雇用保険ですが、2028年10月からは「週10時間以上」の労働者にも雇用保険が適用されます。
週10時間以上の労働者も雇用保険の対象とされる背景
改正の背景には、働き方の多様化と、それに伴い雇用に関する支援制度の充実が求められていることが挙げられます。
近年では、パートタイムやアルバイトなど、短時間労働を選択する人が増加しており、2023年時点で、週の所定労働時間が20時間未満の労働者が約506万人に達しています。
こうした短時間労働者のなかには、雇用保険の対象外となるために、失業時や育児・介護などのライフイベントに直面した際に、十分な支援を受けられないケースが見受けられます。
そのため、雇用保険制度の対象を「週10時間以上働く労働者」にまで拡大することで、より多くの人が万一のときにも必要な給付を受けられるようにし、就労の安心感を高めることが狙いとされています。
企業側にとっても、安定した労働力の確保や人材の定着につながることが期待されています。
参考:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」
雇用保険適用拡大に伴う基準改定
週10時間以上働く従業員も雇用保険の対象となることで、制度全体の整合性を図るために給付金の基準もあわせて見直されます。
ここでは、以下2点の基準改定について解説します。
- 被保険者期間の算定基準の緩和
- 失業認定の基準の変更
被保険者期間の算定基準の緩和
現行では、雇用保険の被保険者期間として1ヶ月とカウントされるためには、「賃金の支払い対象となる日数が11日以上」または「労働時間が80時間以上」である必要があります。
2028年10月の改正後は「6日以上」または「40時間以上」に要件が引き下げられ、短時間労働者にとっても被保険者期間を積みやすくなります。
失業認定の基準の変更
現行では「1日の労働時間が4時間未満」であれば、その日は失業日と認定されていましたが、改正後は基準が「2時間未満」に引き下げられます。
この変更により、時短勤務をしながら求職活動を行う方も、適切に失業給付を受けられるようになります。
今後の雇用保険法改正に伴う企業の対応
2025年から2028年にかけて段階的に実施される雇用保険制度の法改正により、企業には主に以下4点の対応が求められます。
- 就業規則や雇用契約書の見直し
- 社内の対象者を調査
- 従業員への制度周知
- 事務手続きの増加に伴う業務フローの見直し
特に、週10時間以上勤務する短時間労働者の適用範囲拡大は、多くの企業にとって大きな制度転換となるため、早期の準備と社内体制の整備が重要です。
それぞれの対応内容について詳しく解説します。
就業規則・雇用契約書の見直し
教育訓練休暇給付金の創設に伴い、従来の就業規則に新たな「教育訓練休暇」を追加する必要があります。
この休暇制度を適切に運用するためには、対象者・取得条件・申請手続きの流れなどを規定に明記し、社内での取り扱いを明確化しておくことが求められます。
また、2028年10月から週10時間以上勤務する従業員への雇用保険適用が予定されていることから、雇用契約書(労働条件通知書)についても「雇用保険の適用あり・なし」に関する記載や、労働時間・就業形態に応じた記載内容の見直しが必要です。
社内の対象者を調査
子の出生後、休業支援給付金や育児時短就業給付金の対象者を社内で調査する必要があります。
特に育児時短就業給付金は、2025年4月時点で時短勤務している従業員も対象となる可能性があるため、早期の確認と説明が求められます。
また、雇用保険の適用拡大に備え、週10時間以上勤務する従業員の調査もしておきましょう。今後新たに雇用保険に加入すべき従業員の人数を把握し、改正に備えて対策を事前に検討することが大切です。
従業員への制度周知
失業給付や育児休業給付、教育訓練休暇給付金などを分かりやすく説明するため、社内説明会やイントラネットで制度周知を行いましょう。
なかには「雇用保険に加入したくない」といった声もあるかもしれません。その背景には、保険料負担への不安や制度理解の不足が考えられます。
企業としては、制度の意義や万一のときに受けられる保障内容を具体的に説明し、従業員の安心感を高める取り組みが求められます。
事務手続きの増加に伴う業務フローの見直し
新たな給付金の創設や適用拡大により、事務手続きの業務負担が大幅に増加することが予想されます。そのため、現行の業務フローや人員体制を見直し、効率的に運用できる仕組みへの再構築が必要です。
例えば、給与計算システムの更新や、勤怠管理システムとの連携を図ることで、手動での処理負担を軽減し、正確なデータ管理が可能になります。
また、雇用保険資格取得・喪失手続き、給付金申請手続きの増加に伴い、事務作業の負担が大きくなるため、電子申請が可能な労務管理システムの導入もおすすめです。
クラウドベースの社会保険労務システム「ARDIO」は、給与計算システムとの連携が可能で、法改正に伴う事務手続きの効率化を加速します。企業は業務負担を大幅に軽減でき、スムーズな制度移行が可能になるでしょう。
まとめ:今後の雇用保険法改正に備えて早めの準備を
今回の雇用保険法改正は、短時間労働者の保護強化や、働く人々への新たな支援策の導入を通じて、労働市場全体の安定化を狙った大きな制度改革です。教育訓練休暇や新設される給付制度への対応など、企業としても早期の社内整備が求められます。
今後の雇用保険法改正に対応するには、手続きのデジタル化が欠かせません。電子申請に対応したクラウド型社会保険労務システムを導入すれば、複雑な手続きの省力化やミスの削減が可能になり、担当者の業務負担を大幅に軽減できます。
制度改正への備えは、企業にとってコスト管理や人事業務の効率化にも直結します。将来を見据えた早めの対策として「ARDIO」などのシステム導入をご検討ください。
著者プロフィール
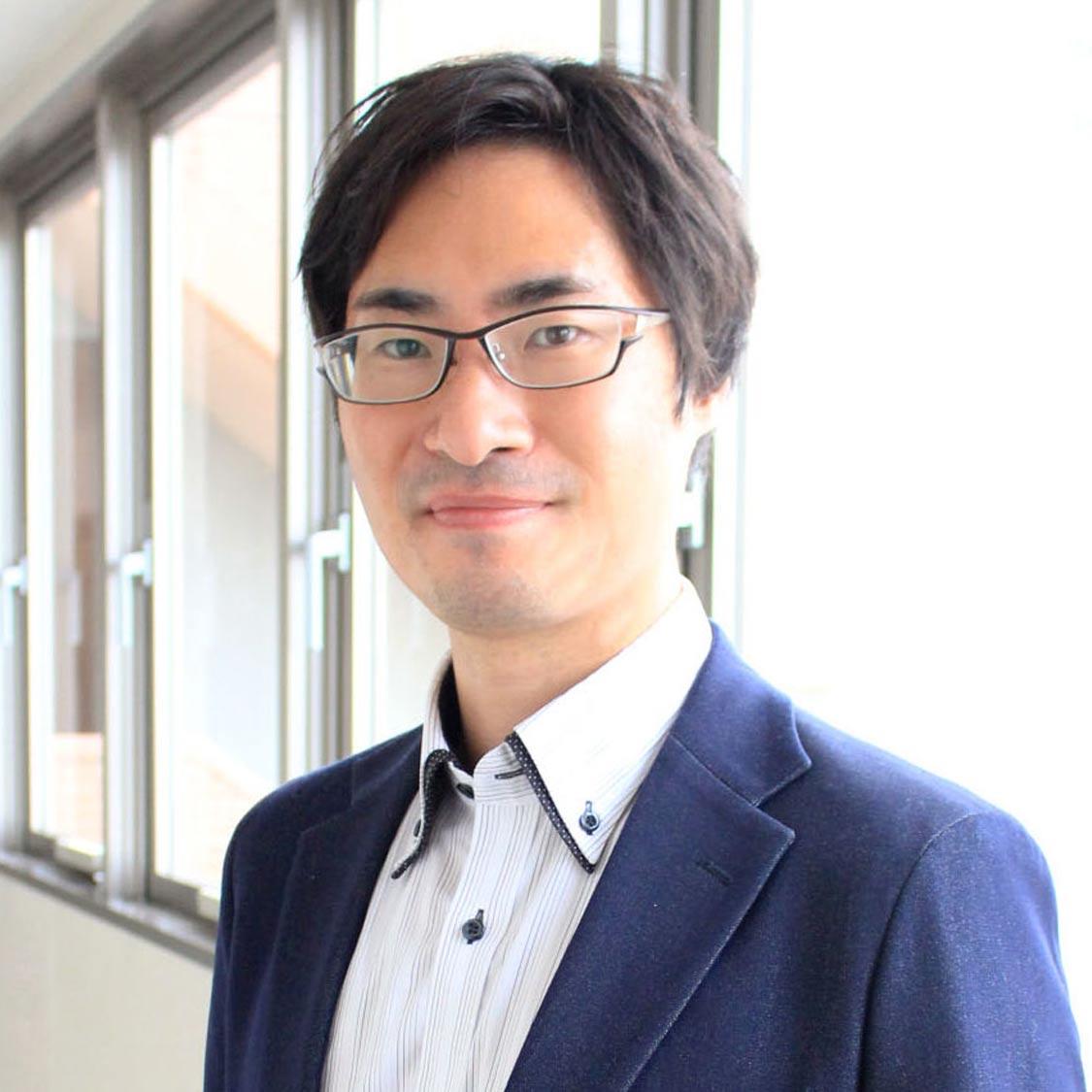
北 光太郎
社会保険労務士
中小企業から上場企業まで様々な企業で労務に従事。勤務社労士として計10年の労務経験を経て「きた社労士事務所」を設立。独立後は労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人・個人問わずWebメディアの記事執筆・監修を行いながら、自身でも労務情報サイトを運営している。
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら