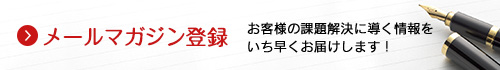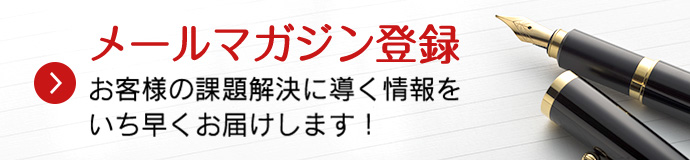在庫管理をもっと分かりやすく。適切な在庫管理を実現する必要性とポイントを解説
日々の業務に追われて、在庫管理を後回しにしていませんか?
在庫が増え、商品が売れず、資金繰りに影響していく。それは決して珍しい話ではなく、在庫を有する企業に共通する"静かな課題"です。課題を解決できるうちに適切な在庫管理を実現することで、経営は確実に変わります。
この記事では、現実的なステップで在庫管理を改善するためのポイントを紹介します。
【目次】
- 在庫管理は「儲けの起点」
- 売上を損失する「見えないロス」
- 在庫を整えること=「売る準備」を整えること
- システム導入で現場はここまで変わる
- 適切な在庫管理を実現する3ステップ
- まとめ
在庫管理は「儲けの起点」

在庫管理というと「コスト削減」や「業務効率化」をイメージする方が多いと思いますが、それは間違いではありません。
しかし、在庫管理は単なる“整理・整頓”の話ではなく、“売上を最大化するための仕組み作り”です。
商品(製品)を適切なタイミングで出荷できるように、倉庫内の適切な場所に置く。この当たり前のようで難しい状態を作り出すために、適切な在庫管理が欠かせません。
売上を損失する「見えないロス」
物流の現場では売上を左右する「見えないロス」が散見されます。
(例えば……)
- 売れ筋の商品が欠品
- 不動在庫がスペースとキャッシュを圧迫
- 商品のロケーションが分からず、出荷までに時間がかかる
- 入荷予定が把握できず、受注機会を逃していた
- 倉庫間で在庫を移動できず、商品が眠っていたなど
こうした在庫に関するロスは業務効率を阻害するだけでなく、売上の損失につながります。
ここからは、見えないロスによってどのような影響が起こるか、具体的に見ていきましょう。
売れ筋の商品が欠品
出荷履歴が残っておらず、需要予測ができずに欠品が発生。売れる商品の在庫切れにより、結果的に得意先からの信頼を失います。
(例えば……)
繁忙期を迎えると、特定の取引先向けに大量注文が入る商品があります。担当者は「そろそろ在庫が減っているだろう」と感じていたものの、明確に確認をしないまま受注が続きました。
その結果、繁忙期に商品を出荷する段階で在庫切れが判明。発注から納品まで数日を要することになり、本来即納できるはずの取引を失注しました。
改めて確認すると、同一商品の在庫が他の倉庫に若干数残っていたものの、倉庫間で在庫移動する仕組みが整っておらず、活用できない状態でした。
【結果】
- 納品リードタイムに間に合わず、失注により相当の売上を損失
- 得意先からは「なぜ在庫が切れるまで気づかないのか」と叱責を受ける
- 得意先は別業者の同カテゴリ商品を陳列。販売スペースを失うことに
不動在庫がスペースとキャッシュを圧迫
“動かない商品”が倉庫を占拠し、売れる商品を置くスペースが確保できない状態です。キャッシュフローも悪化します。
(例えば……)
<1>食品・日用品など、シーズンやトレンドに左右されやすい商品(例えば、夏季限定商品やハロウィンのお菓子など)の在庫を「売れる」と見込んで多めに仕入れたものの、見込みが外れ相当数が売れ残った。
<2>特定の得意先(大口取引先)向けに、ラベルや仕様をカスタマイズした専用品を在庫していたものの、急に取引が減少(もしくは終了)した
【結果】
- 時期を外れると価値が大きく減少する商品の死蔵が発生。廃棄にかかる不必要なコストが発生
- 他の商戦で流用できない商品が倉庫に積まれたままに。次の季節商品を置くはずのスペースを圧迫
- 倉庫内のスペースを恒常的に圧迫し、ピック効率が悪化
- 売れ筋商品の置き場所を確保するために、外部倉庫を契約。本来は不要な費用の発生によりキャッシュを圧迫
商品のロケーションが分からず、出荷まで時間がかかる
複数の場所に在庫が点在し、商品を探す時間や移動時間がかかることで業務効率が低下し、ミスピックや誤出荷のリスクも高まります。
(例えば……)
<1>雑多なロケーション運用による探し物の常態化
定番商品は「棚番号」で在庫管理する一方で、キャンペーン商品や季節商品は「空いている場所に仮置き」で運用。その結果、同じ商品が3〜4ヶ所に保管されていた。
<2>紙や口頭オペレーションによる属人化
【結果】
- 商品の出荷時に探す時間がかかり、リードタイムが伸びる。出荷遅延により取引先から信頼を失うなどのペナルティが発生
- 商品の場所を熟知している作業者が休むと作業が回らない
- 棚卸の際にも「在庫があるのに見つからない」という事態が頻発。棚卸にかかる時間が伸び、通常作業の遅延が発生
- 誤出荷(例えば、想定と異なるロットや賞味期限の商品など)によりクレームが発生し、取引が停止
- 緊急出荷の依頼に対応できず、取引先の発注先が別の業者に移る
入荷予定が見えず、受注機会を逃していた
既に発注済みの商品が「いつ」「何が」届くかを営業や現場スタッフが把握しておらず、「在庫がない」と判断して販売を見送ってしまう場合があります。
(例えば……)
<1>現場スタッフからの問い合わせに「◯◯の型番がない」と報告。調達担当が急ぎで手配したものの、実は2日前に同じ商品を発注済みで来週入荷予定だった。
<2>展示会でバイヤーから「このバッグは再入荷しますか?」と質問があった際に、現場担当者は「再入荷の予定はありません」と答えてしまい、商機を逃した。
【結果】
- 二重発注により、在庫が過剰に
- コンスタントな売上が期待できない商品によって倉庫スペースが逼迫し、死蔵となるおそれも
- 「調達が適当だ」「現場が無駄な報告をする」など、社内で責任のなすり合いが発生
- 適切な提案ができずに商談がまとまらず、失注。バイヤーは同様の商品を他社から仕入れる。信用の低下により売り上げが減少
倉庫間で在庫移動できず、商品が眠っていた
需要の高い商品が別の倉庫で“眠った”ままに。拠点間で商品を動かす仕組みがないことで、在庫の死蔵が発生します。
(例えば……)
<1>特定の得意先(大口取引先)の定期的な案件において、必要な商品がA倉庫では在庫切れ。B倉庫に在庫はあるものの、B倉庫からの出荷は契約外として対応できなかった。
<2>関東の倉庫に大量に残った季節商品(例えば、夏用のレジャーグッズなど)は、関西の催事で売れる見込みがあった。しかし「輸送費がもったいない」との理由で社内調整が進まず、移動できないまま商機を逃した。
【結果】
- 本来売れるはずの季節商品が不良在庫化
- 来年には型落ちとなるため返品・処分対象に
- 一方、別拠点では「売れ筋商品が足りない」とクレームが発生
- 売上を確保できず、業績目標に届かないおそれも
こうした在庫管理の課題は、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。では、こうした課題や問題の発生を防ぐには、どのような施策が必要となるのでしょうか?
在庫を整えること=「売る準備」を整えること
前述したロスの多くは、社内の連携を強化し適切に管理することで防げます。
作業者の「経験」や「勘」に依存する属人的な在庫管理では、精度・スピードともに限界があります。そこで、今、現場に求められているのは「仕組みで回す在庫管理」です。
在庫管理とは、商品の出入りの管理にとどまらず、“売れる状態”を作るための活動です。つまり、売るための“準備(仕込み)”といえます。現場で活用できるシステムを導入し、適切な在庫管理を実現するための準備を整えることで、数字(売上)がついてきます。
システム導入で現場はここまで変わる
在庫管理の精度とスピードを上げるためには「在庫管理システム」が欠かせません。一方で、経営者にとっては「本当に必要か?」「使いこなせるのか?」という不安もあるでしょう。
まずは、システムの導入で得られる具体的なメリットを解説します。
在庫の可視化
Excelや紙の台帳では限界がある在庫管理も、システムを導入することで「今、どの商品がどこにいくつあるか」を一目で把握できるようになります。利便性の高さはもちろん、「判断のスピード」が大きく変わります。
倉庫にある目の前の商品だけでなく、発注した商品の入荷予定も把握し、在庫管理システムに反映することで、売上機会を逃すことなく注文を受けられます。
また、売れ筋商品の在庫状況をすぐに把握できるため「気づいたら欠品していた」「仕入れすぎて在庫が山積み」といった無駄を防げます。結果的に“売り逃し”が減り、キャッシュフローの改善に役立ちます。
複数の倉庫と連携した在庫管理
倉庫が複数ある場合、在庫管理システムの導入により、倉庫ごとの在庫管理が可能です。倉庫間で商品をフレキシブルに移動でき、「動いていない在庫=お金が寝ている」状態を防ぐことができます。
属人化の排除
作業者の「経験」や「勘」に頼らなくても、誰が見ても同じ判断ができる状態を作れます。また、業務の引き継ぎや共有もスムーズになり、現場の安定感も増すでしょう。
適切な在庫管理を実現する3ステップ
適切な在庫管理を実現するためには、段階的に進めていく戦略的アプローチが欠かせません。以下の3ステップは「適切な在庫管理」を実現する基本設計です。
在庫の可視化:商品が“あるかないか”ではなく、“見えているかどうか”
在庫の可視化とは、単に在庫が「ある」「ない」だけを確認することではありません。大事なことは「何が、どこに、いくつ、いつからあるか」を、誰が見てもすぐに分かる状態を作ることです。
物流の現場では、以下のような課題を抱えがちです。
- 在庫はあるものの、置いてある場所が分からず、すぐに出荷できない
- 一部のスタッフしか把握していない“暗黙の場所ルール”がある
- 棚卸のたびに、現場の状況とデータが合わない
- 入出荷の記録が手書きで、リアルタイムに在庫が更新されない
こうした在庫が「見えていない」ことによるロスによって、売上や利益を逸するリスクがあることを、全社で認識・共有しなければなりません。
可視化により実現すること
- リアルタイムの在庫確認:パソコンやスマートフォンを通じて「今、いくつあるか」が即座に把握できる
- ロケーション管理:商品の場所がシステム内のマップ・ラベルで明確になり、商品を探し回る時間を大幅に削減
- 棚卸の簡略化:在庫の差異が可視化され、棚卸のミスが減る
- 属人化の排除:誰でも同じ情報にアクセスでき、引き継ぎや応援もスムーズに
可視化は、在庫の状態を正確に把握することです。ここを疎かにすると、在庫に関わる分析や改善は“感覚ベース”に逆戻りします。
ABC分析による優先順位付け
全ての商品を同じ精度で管理することは非効率です。「売れる商品」や「利益が出る商品」にこそ、優先的に時間と手間をかけるべきです。
そこで、ABC分析により商品を「売上貢献度」や「回転率」の高い順に分類します。
- Aランク:売上の大半を占める重要商品。常に在庫を切らさないことが最優先
- Bランク:安定して売れるもののAランクほどではない商品。適切な在庫を保ち続ける
- Cランク:動きが鈍く、在庫リスクが高い商品。 在庫を減らす、もしくは 廃棄・入れ替え対象に
ABC分析を定期的に行うことで「今、管理すべき在庫はどれか?」が把握しやすくなります。発注精度が高まり、売上管理など各業務の合理化も実現可能です。
“動く”在庫の仕組みを作る
在庫管理の理想は「止まっている在庫がなく、常に商品が動いている状態」です。つまり「入ってきた商品が、必要な場所に流れ、売れていく」リズムを作ることといえます。
その実現には、以下のような仕組みが有効です。
- 発注タイミングの明確化:「いつ、いくつ仕入れるか」をデータベースで管理
- 適切なロケーションの実現:売れる商品を取り出しやすい“一等地”に配置
- 不動在庫の定期処理:売れていない在庫を可視化し、販促・値下げ・廃棄を判断
- スタッフオペレーションの統一:誰が作業しても“動線”が狂わないようにマニュアル化
「“動く”在庫=利益が回る現場」を実現することで、売上・商品回転率・キャッシュフローが連動して改善します。
まとめ
在庫管理の改善は、売上を最大化するカギを握っています。改善によって在庫が可視化され、“動く”在庫を実現する仕組みが整えば、現場は劇的に変わります。
最後に、適切な在庫管理を実現するための3つのポイントをおさらいします。
1. 在庫の可視化
現状把握を徹底し、「何が」「どこに」「いくつあるか」を即座に確認できる状態を作る。業務効率化とミスの削減を実現し、在庫ロスを防ぎます。
2. ABC分析による優先順位付け
売上貢献度や回転率に基づいて商品をランク分け。売れる商品にリソースを集中させ、売れない商品は早めに対処することで、無駄な管理時間やコストを削減。
3. “動く”在庫の仕組みを作る
在庫が常に“動く”状態を作るために、発注管理・ロケーション整理・不動在庫の処理をシステム化。
在庫管理は売上に直結します。こうした仕組みを整えながら適切な在庫管理を実現することで、売上や利益に大きく好影響を与えることができます。
卸売業(倉庫)の適切な在庫管理の実現には「販売指南」が役立ちます。
【販売指南を導入する主なメリット】
▼倉庫が複数ある場合、それぞれの倉庫ごとに在庫管理が可能。商品をフレキシブルに倉庫間で移動できるため、注文を受けたあと柔軟に出荷できます。
▼未来在庫(発注済で入荷予定日が分かっている商品)もシステムに反映可能。現在、倉庫に商品がなくても未来の在庫(入荷日)を把握しやすくなり、注文を受けることが可能に。売上機会の損失を防ぎます。
著者プロフィール

芳賀 俊亮
物流コンサルタント(フリー物流マン)
2022年にフリーコンサルタントとして独立し『HAGA LOGISTICS(CLO)』を設立。「物流のモヤっとしたものを解決します。」をモットーに物流業界での知見を活かしながら、百貨店のサブスク事業の立ち上げ支援や倉庫会社の業務改善などを担う。一方で中小企業やスタートアップ向けの物流セミナーを定期的に開催し、物流改善や在庫管理改善に関する啓蒙活動にも取り組んでいる。
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら