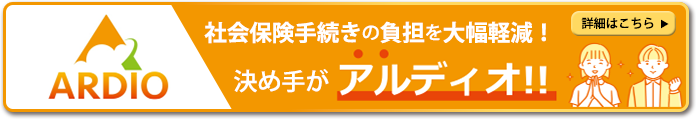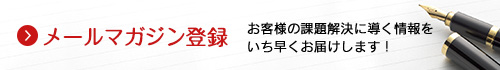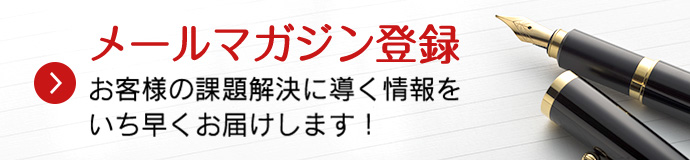大企業がスムーズに健康保険組合への電子申請を進めるポイント
2020年11月から「資本金1億円超の法人など」を対象に、健康保険組合への電子申請が義務となりました。協会けんぽへの申請はデジタル化が進み、e-Govを経由した電子申請が普及する中、健康保険組合への電子申請対応がいまだ進まない企業も存在します。
健康保険組合への電子申請はe-Gov非対応のため、マイナポータルと連携した外部サービスを利用し申請します。健康保険組合の加入企業は大企業が多く、各地に拠点や部署を置いているため業務フローが複雑になりがちです。入退社する従業員の多さも影響し、電子申請対応の遅れを引き起こしています。
2024年12月1日をもって紙の保険証が廃止となり、1年間の移行期間を経てマイナ保険証に移行するなど、デジタル化への対応が欠かせません。そこで、本記事では健康保険組合への電子申請の概要や現状、メリットに加え、大企業が課題を解決するためのポイントも交えて解説します。
健康保険手続きの電子申請とは

2020年4月から「資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人」などの特定法人を対象に、社会保険・労働保険に関する一部の手続きについて電子申請が義務化されました。
健康保険関連の電子申請は、大きく2つの手段があります。1つは協会けんぽの加入事業者が用いる『e-Gov』、もう1つは健康保険組合の加入事業者向けの『マイナポータル』です。健康保険の運営主体(保険者)により使用するシステムが指定されています。
電子申請をサポートする市販のソフトウエアは複数存在しますが、最終的にはe-Govやマイナポータルを経由して申請します。
マイナポータルとは
マイナポータルは、国が提供するオンラインサービスです。年金の納付状況の確認や児童手当の申請など、各種行政手続きをより簡単に行えるシステムで、行政サービスの利便性を高めます。
e-Govとマイナポータルの違い
e-Govとマイナポータルは、それぞれの役割に明確な違いがあります。e-Govは法人や個人事業主の行政手続きをオンラインで行うための事業者向けサービスです。
マイナポータルは個人向けのオンラインサービスで、健康保険組合が運営する保険に加入する場合、マイナポータルを利用して雇用主(企業)に必要な情報を通知することで申請可能です。
紙の保険証廃止、マイナ保険証への移行
デジタル化推進の一環として、2024年12月1日をもって紙の保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が開始しました。
なお、1年間の移行期間中は特例的に紙の保険証も従来通り利用可能です。
健康保険組合への電子申請対応が進まない理由
社会保険における手続きにおいて電子申請の普及が進む中、健康保険組合への電子申請は普及しきれていません。その理由は主に2つあると考えられます。
1.健康保険組合の電子申請はe-Gov非対応
健康保険組合に関連する電子申請は、e-Govが対応していません。
協会けんぽの場合は、e-GovのWebサイトにログインして直接電子申請できるため、新たなソフトウエアの導入は不要です。業務効率はさておき、ソフトウエアの導入に費用をかけることなくe-Govだけで電子申請を完結できます。
一方、健康保険組合の電子申請はe-Govに対応しておらず、マイナポータルと連携した外部サービスを利用して申請する必要があります。
外部サービス導入にかかる費用や各種対応時に要するコストが、対応の遅れを引き起こす一つの要因となっていると考えられます。
2.企業規模に起因した業務フローの複雑化
健康保険組合は、主に常時700名以上の従業員を雇用する会社が設立・運営しています。よって、大企業もしくはそのグループ企業など経営規模の大きな企業が対象です。
こうした大企業では、従業員の入退社が毎月のように行われており、従業員数をはじめ、配属部署や拠点の多さから、採用・退職時の業務フローが複雑化しがちです。そのため、業務フローの変更を伴う電子申請の導入が進まない場合があります。
健康保険組合への電子申請を導入するメリット
上記で解説した理由を背景に電子申請が進んでいない状況もありますが、健康保険組合が電子申請を導入するメリットは少なくありません。
1.業務効率の向上
電子申請を活用する最大のメリットは、業務効率の向上です。従来行われていた紙ベースによる手続きでは、書類の印刷、記入、郵送と手間がかかります。もし、不備があれば紙や電話での修正が必要で、多くの時間と労力を要していました。
一方、デジタルによる電子申請ではこうした一連のプロセスを効率よく進められ、業務時間の大幅な短縮が可能です。手書きや手入力によるミスが大幅に減少し、郵送時の手間や遅延を防ぐとともに、郵送書類の未達の不安もなくなります。
スムーズで正確に手続きを進められる電子申請により、業務時間を短縮し別のコア業務にリソースをかけられます。
2.各種費用の削減
電子申請の導入によるもう一つの大きな利点は、コスト削減です。紙ベースの手続きでは、書類の印刷費や郵送費、さらには人的コストがデジタルでの手続きと比べて多く発生します。
紙ベースの手続きにかかる費用は、一見すると小さな額に思えるかもしれません。ですが、年間を通じて積み重なると大きなコストになります。
一方、電子申請を導入することで、こうしたコストを大幅に削減可能です。これまで手作業で行っていた業務の一部をデジタル化することでスピーディに効率よく業務を進められるため、人件費の削減も期待できます。
特に給与水準の高い大企業は、こうしたコスト削減の効果は顕著に現れるでしょう。
3.コンプライアンスの向上
現代の企業経営は、法令順守や内部統制の強化が欠かせません。コンプライアンスはあらゆる企業にとって遵守すべき点ですが、特にステークホルダーが多い大企業はより一層意識すべきポイントといえるでしょう。
その点を踏まえると、コンプライアンスの向上にも電子申請が役立ちます。電子申請の導入により申請データをシステム上で一元管理し、申請内容がシステム上で自動的に記録・保存されることにより、不正やミスを防止する仕組みを構築できます。
こうした内部統制の強化に加え、監査時に柔軟に対応できる点も大きなメリットです。
健康保険組合への電子申請対応における課題
導入するメリットの大きい電子申請ですが、健康保険組合の加入企業においていまだ導入が進んでいない場合も散見されます。その背景には、以下の2点が考えられます。
1.システム導入時のトレーニングコスト、及び人的負担
マイナポータルを経由して行う電子申請には、専用システムや外部サービスを導入するためのコストのほか、新しいシステムを操作するための担当者トレーニングにかかる人的コストが発生します。
また、新たなシステムの導入による業務フロー変更に抵抗感をもつ担当者もいるでしょう。長年にわたり確立された紙ベースの手続きに慣れている担当者ほど、電子申請への対応に時間を要することが予想されます。
2.自社にマッチした最適な外部サービスの選択
マイナポータルと連携可能な外部サービスは多岐にわたります。それぞれのサービスは異なる特徴があり、各サービスにおける機能性、操作性、コスト、サポート体制などを比較し、自社の規模や業務フローに適したサービスを選ぶ必要があります。
ただ、大企業は関連部署が多く、稟議なども含め意思決定までの時間が長期化する場合が想定されます。複数のサービスを比較し社内提案するまでに調整が不可欠で、こうしたプロセスの存在が電子申請の導入を妨げる要因の一つと考えられます。
大企業が電子申請対応を進めるためのポイント
企業における電子申請システムの導入は、業務効率化やコスト削減、コンプライアンス強化の観点から、ますます重要性を増しています。
特に従業員数が多い大企業は導入効果が見込める反面、自社の状況にフィットする適切なソフトウエアの導入や運用が求められます。
大企業が電子申請対応を円滑に進めるためのポイントについて、2つの観点から詳しく解説しましょう。
1.システム導入の計画
電子申請システムの導入時には、計画的かつ段階的に進めます。自社に合った方法で導入時に対応することで混乱や予期せぬ問題の発生を防ぎ、円滑に導入できます。
① 現状分析
まずは現状の業務フローを徹底的に細分化し、課題や問題点を洗い出しましょう。
例えば、「どのプロセスで手作業が多いのか」「郵送の頻度はどのくらいか」「直接、健康保険組合に出向くことはあるか」など、手続きに関する現状の課題を洗い出し、電子申請の導入後にどのような改善効果が期待できるポイントを明確化します。
分析段階で、各部署や業務担当者とのヒアリングを重ね、現場の声を漏れなく聞き出すことが重要です。
② システムに求める機能の確認
次に、新たなシステムに求められる機能や要件を明確にします。具体的には、申請データの作成方法や既存の社内システムとの連携機能、セキュリティー要件などを確認し、自社のニーズにマッチしているシステムを検討しましょう。
2.適切な電子申請システムの選定
マイナポータルと連携可能な外部システムの導入時には、以下の3点で検討を進めます。
① 費用対効果の検討
新たなサービスの選定時には、初期導入費用や利用料、保守料だけでなく、導入後に得られる業務効率の改善やコスト削減などの効果をもとに検討します。
検討前に印刷費や郵送費といった各費用など、これまでに要していたコストが「どのくらい削減できるか」を検討しておくとイメージしやすく、提案しやすくなります。
② 操作性の確認
従業員が日常的に利用するシステムであるため、操作性は重要な選定基準となります。
システムのUI(ユーザーインターフェース)が直感的で使いやすいものであれば、担当者の抵抗感を和らげ、導入後の定着がスムーズに進みます。
③ サポート体制の評価
導入後の運用が滞りなく進むよう、外部サービス提供企業のサポート体制を事前に確認しておきましょう。
例えば、トラブル発生時に迅速に対応可能な窓口があるか、システムのアップデートや改善提案を定期的に行ってくれるかなど、導入後のサポート体制も貴重な評価ポイントです。
まとめ
健康保険組合への電子申請対応は、e-Govの非対応や入退職者数の多さなど、大企業特有の課題から導入が遅れている状況があります。
しかし、電子申請の導入により業務に要する時間や費用などのコスト削減、コンプライアンスの向上などのメリットが少なくありません。こうしたメリットは特に大企業ほど顕著です。
大企業が電子申請への対応を進める際には、適切なソフトウエアの選定やサポート体制を踏まえて、計画的に導入を進めていくことポイントです。本記事で解説したポイントを参考に、自社にとって最適な電子申請対応をぜひ検討してください。
著者プロフィール

渋田 貴正
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、証券アナリスト、上級相続診断士。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務
を行う。
「業務改善」の最新記事
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら