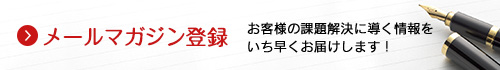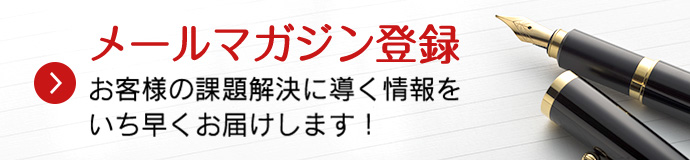EDIとは? EDIの導入で実現できる劇的な業務効率化やコスト削減
近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、企業間取引の効率化が加速しています。
「改正電子帳簿保存法」の施行など、書類の電子化が推奨される中で「EDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)」は、業務効率を大きく向上させるツールとして注目を集めています。
本記事では、EDIの基礎知識やEDI導入による業務効率の向上について、導入プロセスも交えながら解説します。
EDIとは

デジタル技術の急速な進化により、企業間取引を取り巻く環境は大きく変化を遂げました。EDIは、これまでFAXや紙媒体を利用して行ってきた取引をオンラインで行い、データをやり取りするフローを標準化することにより、企業間の取引情報を正確にかつリアルタイムに共有する仕組みです。
これまでEDIは、大企業とその取引先や特定業界において利用されていました。しかし、近年では中小企業にもDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せ、業務効率化を図る有効手段として導入が進みつつあります。
EDIの種類
EDIには、いくつかの種類があります。
・個別EDI
企業ごとに独自の規格を設け、特定の取引先と専用回線でデータをやり取りする方式
・標準EDI
業界や地域などで統一された規格を採用し、複数の企業間で共通のEDIフォーマットを
利用する方式
・業界VAN
特定の業界内でEDIネットワークを提供するサービスを利用する方式
大企業や特定の業界では「個別EDI」や「業界VAN」が主流でした。
中小企業への普及が進むEDI
従来のEDIは、大企業が取引先に導入を求めるケースが多く、中小企業にとってはコストやシステムの互換性の問題がハードルとなっていました。
しかし、近年は多くの企業が取引のデジタル化に取り組む時代となり、「WEB-EDI」の普及や「中小企業共通EDI」の登場により、中小企業でもEDIの導入が進んでいます。
「中小企業共通EDI」は、異なる取引先間でも統一された規格でデータ交換を可能にし、企業ごとに異なるEDIシステムに対応する負担を軽減する仕組みとして活用されています。
従来の企業間取引における課題
従来、EDIなどのシステムを用いていない中小企業では、企業間取引における多くの業務を企業独自のシステムで行なっていました。こうした取引の際には、いくつかの課題があります。
管理コストの発生
書面を紙で作成している場合には、印刷・郵送・保管にかかる費用が負担となります。金額的なコストにとどまらず、保管スペースの確保や保管期間経過後の廃棄の際にも費用が発生します。
また、紙での長期保存は経年劣化や紛失のリスクが伴います。必要な情報を確認する際にも時間を要するため、業務効率を低下させる大きな要因となります。
業務ルールの違い
取引先ごとに帳票のフォーマットや提出方法が異なる場合、各取引先に応じた業務フローで作業を進める必要があります。
複数のフォーマットに対応する必要がある場合、業務の標準化が進まず、業務効率が低下します。
また、社内で特定の担当者しか対応できない場合、業務の属人化を招きがちです。担当者が不在の場合など、業務をスムーズに進められないリスクが生じます。
二重入力の手間
多くの企業では複数の業務システムを併用しており、それぞれのシステムに同じデータを入力する場合があります。
二重入力の手間は、時間を無駄にするだけでなく、入力ミスなどヒューマンエラーの温床になります。
システム間のデータ不整合
システム間でデータの更新がうまくいかず、データの不整合が起こる場合もあります。データの不一致により、取引先とトラブルを起こしかねません。
チェック項目を増やすことによる作業時間の増加や、データの整合性を確保するための修正作業など、本来不要な人的コストが発生します。
EDI導入による改善効果
上記のような課題を解決する手段として、EDIの導入が効果的です。EDIを活用し、EDIからのデータと自社の基幹システムを連携することにより、業務全体の効率化と正確性の向上を実現できます。
自動化によるミス削減
EDIを導入し、基幹システムと自動でデータ連携を行うことにより、それまでは特定のメンバーに依存していた業務の自動化が可能です。
・ヒューマンエラーの削減
データ入力や送信プロセスが自動化されることで、ミスを最小限に抑えられます。
・取引プロセスの標準化
標準フォーマットを用いるためデータの一貫性が確保され、目視によるチェックを減らせます。
コスト削減
EDIの導入は、業務コストを削減する効果があります。
・紙や郵送にかかるコストの削減
印刷費や通信費、保管費などの諸費用を削減可能です。
・業務効率向上による人的リソースの削減
EDIからの取引データを基幹システムと連携させることにより、取引情報の一元管理が実現できます。それにより、社内で情報を共有して横断的に利用できるため、業務がスムーズに進み労働時間の短縮につながります。
・ミス削減によるトラブル対応費用の削減
ヒューマンエラーの減少により、トラブルシューティングに要する時間的なコストや従業員のストレスも軽減できます。
EDIの活用事例
EDIは、企業間取引の効率化による各種コストの削減を可能にするツールとして活用されています。
受発注業務の効率化
EDIからの取引データを基幹システムと連携させることにより、大きく受発注業務を効率化できます。
・自動発注
EDIからの発注情報を基幹システムの在庫情報とリアルタイムで連動させることで、必要なタイミングで自動的に在庫を確認して発注処理を行うことが可能です。在庫不足による機会損失を防ぐことができるほか、発注業務のスピードアップが実現します。
・納品確認の自動化
リアルタイムで納品情報を共有することで、納品確認作業を大幅に簡略化できます。作業効率の向上とタイムリーな対応が可能になります。
サプライチェーンの最適化
EDIの導入は、サプライチェーン全体の効率化にも大きく役立ちます。
・生産・配送計画の最適化
EDIを利用して取引先間で情報を迅速に共有することで、生産計画や配送計画をより精緻に進められます。その結果、過剰在庫による保管コストなど、不要なコストの削減が可能です。
・在庫管理の最適化
EDIの取引データと基幹システムを連携させ、より正確な情報管理を実現することにより、例えば、適切な在庫管理が可能となり、在庫不足や過剰在庫を未然に防止できます。
EDIの導入プロセス
EDI導入までの一般的なプロセスについて解説します。
1.現状の確認
まずは現在の受注や発注に関する業務フローや課題を洗い出しましょう。具体的には、以下のポイントを確認します。
▼手作業が多い工程や非効率なプロセス、ボトルネックになっているプロセス
▼多くのコストを要している業務
▼EDI導入後の基幹システム連携
この段階で課題を正確に把握することでEDI導入の目的が明確になり、より自社にマッチしたシステムの選定が可能となります。場合によっては、EDI導入後の基幹システム連携を踏まえると、基幹システム自体を見直さなければならないかもしれません。
2.システム選定
現状分析を踏まえ、業務内容に最適なEDIシステムもしくはEDIに対応している基幹システムを選定しましょう。選定時には以下の点を確認します。
▼自社の業務規模や取引内容に適合するか
▼導入コストとランニングコストが予算の範囲内か
▼業務拡大時に機能拡張で対応可能か
3.取引先との調整
EDIの導入時には、取引先の協力も欠かせません。データフォーマットの統一や導入スケジュールの通知などのさまざまな調整が必要です。
4.テスト運用
本格運用の前には、必ずシステムのテスト運用を行いましょう。テストでは主に以下の項目を確認します。
▼データ送受信が正確に行えるか
▼システムのレスポンスや動作速度に問題がないか
▼エラー発生時の対処が適切に機能するか
運用時のトラブルを最小限に抑えるためにも、課題点をクリアにしましょう。
5.本格運用
テスト運用後、実際にEDI運用を開始します。取引でトラブルを起こさないように、以下の点に気をつけましょう。
▼運用開始後も定期的にシステムを監視
▼取引先との連携状況を適宜確認し、必要に応じて調整
▼新たな課題や改善点が出てきた場合には、業務フローを変更するなど随時対応
EDI導入成功のポイント
EDIの導入を成功させるために、3つのポイントを意識しましょう。
1.社内外の調整
EDIの導入により、既存の業務フローが大きく変更される場合があります。そのため、取引先や社内の関係部門とスムーズな連携が欠かせません。
▼コミュニケーションの強化
導入目的や手順を社内外に共有し、理解を深める。
▼チームワークの促進
プロジェクトチームを編成し、役割を明確化する。
▼定期的な会議
進捗状況や課題を共有し、解決策を協議する場を設ける。
上記のように情報共有を意識して、EDI導入後の効果的な運用を目指しましょう。
2.セキュリティー対策
EDIでは重要な取引データを取り扱うため、セキュリティーの確保も重要です。
▼暗号化技術の採用
通信データを暗号化し、不正アクセスを防止
▼アクセス管理
データにアクセスできる権限を厳格に管理
▼バックアップ体制の構築
データ消失やシステム障害に備え、バックアップを定期的に取得
3.社員教育
新たなシステムを効果的に運用するためには、社員教育も必要不可欠です。EDI導入後に、仕組みや業務フローを社員が理解できるように取り組み、安定運用を目指しましょう。
▼マニュアルの作成
分かりやすい手順書を用意し、現場で活用
▼トレーニングの実施
実際の操作方法やトラブル時の対応を習得するため、定期的に研修を実施
▼フォローアップ
導入後も疑問点や改善案に対して迅速に対応できる体制を整える
まとめ
EDIは企業の業務効率を向上します。一方で、最大限に活用するには既存の業務フローの再構築や社内外とのコミュニケーション、社員教育などの取り組みが必要です。着実に導入を進めながら、業務効率を向上するEDIシステムの導入を成功させましょう。
著者プロフィール

渋田 貴正
税理士/司法書士/社会保険労務士
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、証券アナリスト、上級相続診断士。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務
を行う。
「業務改善」の最新記事
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら