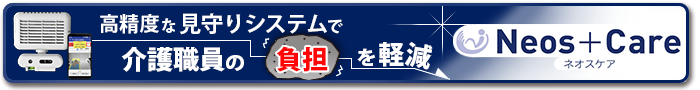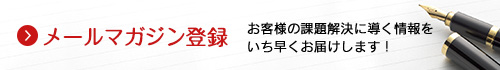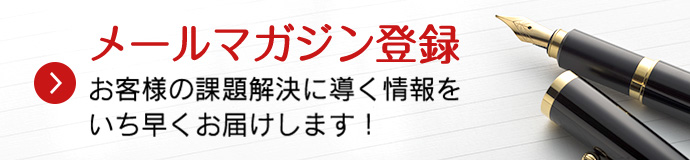介護の事故報告書の目的とは? 実際の事故をもとに記入例や書くときのポイントを紹介
介護現場では、日々さまざまな事故のリスクが潜んでおり、事故が発生した際は「事故報告書」を書く必要があります。
そんな介護現場の事故報告書について、次のような疑問を持っていませんか?
- そもそも事故報告書ってなぜ書くの?
- 事故報告書の正しい書き方は?
- 事故を防ぐための効果的な対策は?
本コラムでは、実際に介護現場で事故報告書を多く作成し、リスク管理に関する知識や経験も豊富な現役介護職員が、事故報告書の目的や記入例、作成時のポイントなどを解説します。
さらに、介護現場の事故防止に役立つ便利なツールも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
介護現場における事故報告書の目的

まずは、介護現場における事故報告書の目的について確認しましょう。事故報告書の目的は、以下の3つです。
- 事故の再発防止
- 介護サービスの質の向上
- 実施した支援内容の証明
それぞれ、詳しく内容を見ていきましょう。
事故の再発防止
介護現場における事故報告書の最大の目的は「事故の再発防止」です。特に、食事中の窒息や薬の間違い事故などは、ご利用者の命に関わるため、適切な再発防止策が必要になります。
介護事故における再発防止策は、ただ実施するだけでは不十分です。実際に再発防止策を実施した結果、リスクが減少したのか評価しなければいけません。
また、再発防止策は継続的に実施する必要があり、介護職員を含めた各職種同士の情報共有も重要です。事故はなぜ起きたのか、適切な支援は何かを分析した上で、効果的な再発防止策を考え実施することが求められるでしょう。
介護サービスの質の向上
介護現場の事故を減らすためには、再発防止策の実施だけでなく、介護サービスの質の向上も求められます。
事故の発生自体は当然防ぎたいものですが、事故が発生した場合は検証した上で、今後の事故防止と介護サービスの質の向上を図る必要があります。
例えば、介護職員の技術不足により、移乗介助時にご利用者を怪我させてしまった場合、あらためて介助方法を職員全体で話し合うことで、チーム全体のサービス向上につなげられます。
実施した支援内容の証明
介護の事故報告書の目的は、排泄介助や食事介助など、実施した支援内容の証明でもあります。
そのため、事故が発生する前後のご利用者の様子や介護職員の介助内容などは、事故内容とともに報告書に記載しておくことが重要です。
実施した支援内容を確実に記録しておけば、ご家族に事故内容を伝える際も、実施した支援内容とともに根拠のある説明が可能となります。
また、万が一事故が原因でご家族が施設や職員に訴訟を起こした場合、事故報告書に記録した支援内容が、トラブルを回避するための証明となる場合もあるでしょう。
介護の事故報告書を作成するまでの手順
続いて、介護の事故報告書を作成するまでの手順を見ていきましょう。具体的な手順は、次のとおりです。
|
事故が発生した際に最も重要なことは「ご利用者の安全」です。例えば、ご利用者が転倒し頭を強く打った場合や、窒息し息ができない場合は、ご利用者の命を守るために緊急的な対応が必要です。
事故が発生した際は無理に1人で対応せず、周囲の職員に助けを求めましょう。夜間に事故が発生し、1人で対応しなければならない場合は、事故が発生しても適切に対応できるよう、緊急時のマニュアルを事前に確認しておくことが大切です。
なお、全ての事故に主治医への報告義務があるわけではありません。例えば、軽い擦り傷や打撲、椅子からのずり落ちによる尻もち程度なら、施設内の記録と管理者への報告だけで済む場合もあります。
ただし、各自治体や施設の方針により、事故報告書作成と主治医への報告を求められるケースもあるため、管理者やリーダーから事前に対応方法を確認しておきましょう。
事故報告書は作成したら終わりではありません。対策を実施し、どのような結果だったかを分析するとともに、職員間での共有も求められます。
そのため、上記で紹介した手順で状況や原因、対策を職員全体で話し合うことが大切です(ご家族への事故内容の報告を介護職員が行う場合もあるため、情報共有は欠かせません)。
介護の事故報告書について知っておくべきこと
介護の事故報告書について、以下3つのポイントも事前に把握しておきましょう。
- 事故報告書は厚生労働省の様式を使用する
- 重大な事故の場合は行政への報告義務がある
- 事故発生後5日以内に市町村へメールで知らせる
行政への報告や市町村への連絡を介護職員が行うことはあまりありませんが、事故報告書に関するルールを理解することは大切です。
それぞれの詳しい内容を確認しておきましょう。
事故報告書は厚生労働省の様式を使用する
事故報告書の作成については、厚生労働省の様式を使用するよう推奨されています。なお、厚生労働省が推奨する様式には、以下の9つの項目が含まれています。
|
<参照> |
厚生労働省の様式を参考に、施設独自で作成している報告書もあります。その場合には、上記の項目が含まれているか確認しましょう。
なお、令和6年11月29日付けで、事故報告書の様式改定がありました。目的は電子的な報告と受付を推進するためで、主な改訂内容は以下のとおりです。
- チェックボックス形式の採用
- 独自項目追加欄の設置
- 電子的報告の推奨
近年、介護業界ではICT化を推進し、職員の負担軽減を図っています。かつてのような手書きの報告書ではなく、電子ツールを利用することで、事故をデータ化し分析しやすくする狙いもあるでしょう。
重大な事故の場合は行政への報告義務がある
死亡事故や医師の処置が必要な重大な事故が発生した場合、行政や自治体への報告義務があります。
厚生労働省も、介護事故の報告対象について、次のように明記しています。
○下記の事故については、原則として全て報告すること。
①死亡に至った事故
②医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
○その他の事故の報告については、各自治体の取扱いによるものとすること。
<引用>
厚生労働省「介護保険最新情報 介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」(令和6年11月29日)
報告は、原則的に施設の管理者が行いますが、事故発生後に各機関への報告義務があることを知っておくことで、介護職員が事故の概要や原因、再発防止策を丁寧に記載する意識の向上につながるでしょう。
事故発生後5日以内に市町村へメールで知らせる
介護施設で事故が発生したら、原則5日以内に市町村へメールで知らせなければいけません。
例え、事故の原因や対策が話し合われていない場合でも、第一報を行政に伝える必要があります。スムーズな連絡を目的としているため、メールでの報告が基本です。
重大事故の報告と同様に、市町村へのメールは原則管理者が行います。介護職員がメールを送ることは原則ありませんが、事故発生後の流れは把握しておきましょう。
なお、ご利用者の状態に変化があれば追加報告を行い、原因や再発防止策が決定し、その後は再発なく経過し事故処理が完了した時点で、結果を最終報告します。
介護の事故報告書を書くときのポイント
介護の事故報告書を書くときのポイントは、以下の5つです。
- ありのままの事実を書く
- 具体的に分かりやすく書く
- 5W1Hで簡潔に書く
- 原因を多面的に考える
- 各職種間で話し合う前に再発防止策を考えておく
それぞれ具体的な内容を確認しましょう。
ありのままの事実を書く
事故報告書を書く際は、事実のみを書きましょう。事実以外のことを書いてしまうと、状況が分かりにくくなり、原因や再発防止策を適切に分析しにくくなります。
例えば、夜間の居室で転倒されたご利用者を発見した場合は「訪室すると床に仰向けに倒れていた」と、事実を記載すれば問題ありません。
しかし、事実以外に「トイレに行こうとしたのかもしれない」や「表情が曇っており落ち着きがないように見えた」など、介護職員の主観が入ると、事実が分かりにくくなります。
まずは、事実を客観的に確認した上で、原因や再発防止策を考える際に、事故に対する推測や考察などを職員間で出し合いましょう。
具体的に分かりやすく書く
事故報告書は文章だけで状況を伝えなければいけないため、具体的に分かりやすく書くことが求められます。簡単なイラストや図を記載する場合もありますが、基本的には文章のみです。
例えば「トイレで転倒していた」という文章だけでは、詳しい状況はイメージが湧きません。そのため「トイレの入り口付近で、身体の右側を下にした状態で倒れていた」といった具体的な状況説明が重要です。
「職員の声かけに対して“大丈夫”と言われる」といった、ご利用者の反応も記載しておくとより具体的に当時の状況を伝えられるでしょう。
5W1Hで簡潔に書く
事故報告書は基本的に「5W1H」で簡潔に書くと、状況が伝わりやすいです。「5W1H」とは、次の6つを表します。
|
|
上記を、転倒事故の状況に当てはめると次のようになります。
|
(例)
|
「5W1H」で基本情報を押さえておけば、報告書を見た際に事故の基本的な状況は伝わるでしょう。
原因を多面的に考える
事故報告書の原因を書く際は、状況を多面的に捉えることが大切です。具体的には、次の3つの視点から考えましょう。それぞれの内容例も紹介するので参考にしてください。
| 原因 | 内容例(転倒事故の場合) |
|---|---|
| ご利用者要因 |
|
| 介護者要因 |
|
| 環境的要因 |
|
上記のとおり事故の原因をさまざまな視点から考えることで、適切な再発防止策につながります。
原因を考える際は普段の様子も考慮しながら、「〇〇の可能性がある」といった推測も含めて導き出しましょう。
各職種のスタッフ間で話し合う前に再発防止策を考えておく
事故報告書の作成後は、介護職員以外の専門職と連携し、事故の原因や効果的な再発防止策を話し合います。ただ、話し合いの場で急に再発防止策を考えるのは、事故現場の様子を知らない職員からすると非効率です。
そのため、事故を発見し報告書を書いた職員(主に介護職員)は、各職種のスタッフと話し合う前に、再発防止策をある程度考えておきましょう。
最終的な再発防止策は、各職種の意見を参考にして話し合った上で決めるため、事前の検討は概要程度で問題ありません。
事故現場を知っている職員の意見と、各職種からの客観的な意見を合わせて検討することで、効果的な再発防止策の立案につながるでしょう。
【記入例】介護現場でよくある事故報告書
最後に、介護現場でよくある事故報告書の記入例を見ていきましょう。今回は、次の3つのケース別に記入例を紹介します。
|
|
それぞれ詳しい内容を確認しましょう。
ご利用者が居室で転倒した場合
ご利用者が居室のベッドサイドの床に転倒していた場合の、事故報告書の記入例は、以下のとおりです。
| 必要事項 | 内容 |
|---|---|
| 事業所名 | A特別養護老人ホーム |
| 利用者名・介護度 | B様・要介護3 |
| 発生日時 | 2024年12月6日(金)23時10分 |
| 発生場所 | B様の居室 |
| 発生状況 | 夜間の巡視のため訪室すると、B様がベッドサイドの床に身体の右側を下にして倒れているところを発見する。状況を聞くと「トイレに行こうとした」とのこと。 |
| 発生後の対応 | 意識確認、外傷チェックするが特に異常なし。転倒時に右肩を打った可能性があるため痛みの訴えあり。立位保持や付き添い歩行は、普段と変わらず可能。念のため、医療職に電話報告し状況説明。湿布を貼り朝まで様子観察の指示あり。 |
| 発生原因 |
|
| 再発予防策 |
|
転倒事故の場合、意思疎通ができる方であれば、何をしようとしたか聞くことが大切です。前後の行動から原因が分かれば、効果的な再発防止策を考えられるでしょう。
この事例のような夜間の居室での転倒事故に対しては、次世代予測型見守りシステム『Neos+Care(ネオスケア)』のような、最新のITツールの導入が効果的です。
▼次世代予測型見守りシステム『Neos+Care(ネオスケア)』はこちら
間違えて他のご利用者の薬を飲ませた場合
続いて、介護事故の中でも重大な服薬事故における報告書の記入例です。
| 必要事項 | 内容 |
|---|---|
| 事業所名 | C介護付き有料老人ホーム |
| 利用者名・介護度 | D様・要介護2 |
| 発生日時 | 2024年12月6日(金)12時15分 |
| 発生場所 | 食堂 |
| 発生状況 | 昼食後、D様とE様から薬を飲ませてほしいとお願いされたため、それぞれの昼食後薬をまとめて持ち順番に服薬介助した。その際に、E様の薬をD様に間違えて飲ませてしまったことに気付く(2人分の薬をまとめてポケットに入れていた)。 |
| 発生後の対応 | すぐに看護師に報告し主治医にも連絡。薬の種類を確認後、下剤のみだったため、応急処置はなし。その後の様子観察の指示あり。D様にはあらためて、ご自分の薬を飲んでいただく。E様に対しては、新しく薬を準備してもらい、服薬していただく。 |
| 発生原因 |
|
| 再発予防策 |
|
服薬事故はご利用者の命に関わる重大な事故のひとつで、ちょっとしたミスが致命傷になる恐れもあります。
服薬事故の多くは、職員側に原因があるヒューマンエラーです。そのため、上記の再発防止策でも記載している、服薬介助に役立つITツールの導入が効果的です。
例えば、服薬介助支援ツール『めでぃさぽ』は、ITを駆使して誤薬を未然に防ぐ画期的なアプリです。アプリによって、服薬間違いが起こる可能性を確実に軽減してくれるでしょう。
▼服薬介助支援ツール『めでぃさぽ 』はこちら
内出血(痣)を発見した場合
3つ目は、介護事故の中でも非常に多い「内出血」を発見したケースです。
| 必要事項 | 内容 |
|---|---|
| 事業所名 | Fグループホーム |
| 利用者名・介護度 | G様・要介護5(寝たきりだが手は動かせる) |
| 発生日時 | 2024年12月7日(土)10時20分 |
| 発生場所 | 浴室 |
| 発生状況 | 入浴介助のため上半身の下着を脱いでいただくと、右前腕に3cm×3cmの内出血を発見する。 |
| 発生後の対応 | 看護師に報告し見てもらう。痛みの訴えはなく、そのほか特に変わりないため、保護テープのみ貼り、その後は様子観察。 |
| 発生原因 |
|
| 再発予防策 |
|
介護事故の中でも多くの割合を占める「内出血」は、原因を特定しにくいという特徴があります。そのため、上記例のように可能性も含めた発生原因を記載することも必要です。
飲んでいる薬の種類によって内出血ができやすくなる薬もあるため、さまざまな角度で発生原因を考える視点も求められるでしょう。
まとめ
介護の事故報告書の目的は「事故の再発防止」をはじめ、「介護サービスの質の向上」や「実施した支援内容の証明」などが挙げられます。もちろん、事故が発生しないほうが望ましいですが、事故報告書を通じて、介護サービスの質向上や職員のスキルアップにつながります。
事故報告書を書く際は、「ありのままの事実を書くこと」や「具体的に分かりやすく書くこと」がポイントです。報告書を適切に書くことでご利用者の生活が改善できます。
ぜひ、本コラムを参考に、効果的な介護の事故報告書の書き方を習得してください。
著者プロフィール

津島 武志
介護系WEBライター
介護業界16年目の現役介護職。介護リーダーや管理職の経験もあり、現在は地方法人のグループホームに勤務。現役の介護職以外に、介護系のWebメディアにおいてのライター活動をはじめ、介護士さんを応援するメディア「介護士の転職コンパス」や「介護士の副業アンテナ」などの運営にも取り組んでいます。主な保有資格は、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士。
メールマガジン登録
上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に
メルマガで配信しています。
コラム(メルマガ)の
定期購読をご希望の方はこちら